第1章 英仏「核運営グループ」創設と欧州抑止体制の強化
ロシアの核の脅威と欧州の安全保障を取り巻く背景
2025年7月10日、イギリスとフランスは、核兵器の運用に関して連携を進める方針で合意しました。英仏両国は共に核保有国であり、国連安全保障理事会の常任理事国という立場も共有しています。この2国が具体的な核運用面での調整に踏み込んだのは、これまでにない一歩だと受け止められています。
合意に至った背景には、ロシアによるウクライナ侵攻の継続と、それに伴う「核の脅し」とされる言動の繰り返しがあります。ロシアが軍事的優位を誇示するなか、欧州の安全保障体制そのものが根底から揺さぶられていると感じる国も増えています。そうした状況下で、英国とフランスが独自に抑止体制を強化し、実効性のある対応手段を講じる必要性が高まったといえるでしょう。
もうひとつの背景として、アメリカの動向が挙げられます。特にトランプ政権のように、欧州の防衛に対する関心が相対的に低くなる可能性が指摘されており、米国主導の安全保障枠組みに全面的に依存することへの懸念も根強くあります。こうした複合的な要因が重なり、英仏両国は連携強化に舵を切ったものと考えられます。
目的は「抑止力の強化」と「迅速な協調対応」
この合意の主たる目的は、欧州の安全保障に対する重大な脅威に対し、両国が迅速に協調して対応できるよう体制を整えることです。両国は核兵器の使用に関する最終的な決定権をそれぞれ保持しつつも、現実的な事態を想定した場合の連携のあり方を再構築する必要があると判断したようです。
スターマー首相はこの合意について、「欧州の2つの核保有国が能力の調整に合意した」と述べ、その意義を強調しました。一方のマクロン大統領も、「極度の脅威が生じた際には、迅速な対応が必要になる」と語り、想定される状況への即応性を重視する姿勢を示しました。
こうした言葉からもわかるように、単なる意思表示ではなく、実際に運用面での実効性を備えた体制づくりを進めていく意図が込められているように見受けられます。
「核運営グループ」の設置とその機能
合意の具体策として、英仏は「核運営グループ(Nuclear Operations Group)」の設置を決定しました。この組織はフランス大統領府とイギリスの内閣府が主導し、以下の3つの領域において調整を担います。
- 核政策の調整
- 核能力の調整
- 核運用全般の調整
この枠組みは、政治的判断と軍事的運用の間を一貫して結びつけるためのものであり、国家間の信頼と透明性を基礎とした実務的な調整機関として機能するとされています。構成メンバーや人数についての詳細は公表されていませんが、両国の政府中枢が直接関与することで、従来よりも踏み込んだ協力が可能になることが見込まれます。
ランカスター・ハウス条約との位置づけの違い
英仏の防衛協力の基盤としては、2010年に締結されたランカスター・ハウス条約が存在します。同条約では、核兵器を伴わない形での性能評価や安全性検証を行うフランス国内の研究施設の共同利用が盛り込まれており、防衛分野全般での協力が規定されていました。
また、合同遠征軍の創設や空母の相互運用性の確保など、有事を想定した装備品や軍事行動の連携も含まれていましたが、いずれも「共同訓練」「研究協力」「装備開発」といった技術・制度面の調整が中心でした。
今回の合意がこれまでと大きく異なるのは、「核兵器の実際の運用を含む連携」にまで踏み込んだ点です。両国がそれぞれの決定権を維持しつつも、核の使用に関して事前の調整と緊急時の情報共有を可能にする体制をつくろうとしている点に、大きな意義があるといえるでしょう。
抑止力強化の具体的展開──核弾頭とミサイル開発
イギリスとフランスが運用可能な核弾頭の数は、それぞれ225発と290発とされています。米国やロシアの保有数には遠く及びませんが、欧州域内における独立した核抑止力としての存在感は小さくありません。
今回の合意により、両国が共同で戦略的な運用方針を整え、意思決定のスピードと相互支援体制を確保することで、抑止効果を高めていくことが期待されます。核保有国同士が調整可能な体制を築くこと自体、他国にとって一定の抑止要因となる可能性もあります。
さらに、両首脳は、巡航ミサイル「ストームシャドー」の次世代型を共同開発することでも一致しました。このミサイルは既にウクライナへの支援にも用いられており、性能向上と供給体制の強化は、抑止力と実戦性の両面において意味を持つと考えられます。
加えて、これまでのランカスター・ハウス条約に基づいて設置された合同部隊の拡大にも合意がなされています。これは核運用に限らず、通常戦力との組み合わせを含めた即応体制の構築に向けた動きとも捉えられます。
第2章 ウクライナ有志国連合──停戦後の安全保障を支える多国間の枠組み
停戦を見据えた新たな国際的連携の形成
イギリスとフランスは、ウクライナに対する安全保障上の支援体制として「有志国連合」の枠組みを主導しています。この取り組みは、停戦後を想定したものであり、単なる一時的な支援ではなく、ウクライナの中長期的な安定を支えるための構造的な安全保障協力と位置づけられています。
この有志国連合が掲げる主要な目的は、ロシアによる再侵略の抑止、停戦合意の履行状況の監視、陸海空にわたる安全確保、そしてウクライナ軍に対する戦術的・後方支援の強化です。これらの要素はいずれも、停戦後の混乱や安全保障の空白を回避し、持続可能な秩序を維持するうえで極めて重要です。
参加国の構成と規模の見通し
有志国連合には、イギリス・フランス・カナダといった核となる国々が既に参加を明らかにしています。さらに、トルコ、オーストラリア、ニュージーランドなどが関心を示しており、最終的には30カ国を超える規模に達する見込みとされています。
ただし、参加国のすべてが部隊派遣を前提としているわけではなく、各国の関与の範囲や負担の在り方については、現在も調整が続いています。軍事的支援に踏み込む国もあれば、人道支援や訓練支援など間接的なかかわりにとどまる国もあることが想定されています。
数日以内の部隊展開──初動対応の準備体制
停戦が成立した場合、有志国連合は数日以内に部隊をウクライナ国内に展開する方針を固めています。この展開は、あくまでウクライナの要請と安全確保を前提とするもので、派遣先はウクライナ側が必要と認めた場所に限定される形を取るとされています。
また、有志国連合による部隊展開は、いわゆる「平和維持部隊」ではなく、前線への配置を伴わない抑止的・支援的な性格を持つものとして位置付けられています。戦闘への直接関与は想定されておらず、あくまでも「停戦後の安全確保に向けた多国間の協調行動」として機能するものと整理されています。
上空の警戒監視体制と航空戦力の活用
部隊展開において中心的な役割を担うのが、有志国連合の航空機による警戒監視です。停戦後に再び緊張が高まるリスクを抑えるため、ウクライナ上空における航空監視体制の確立が不可欠とされており、これを通じて事態の急変や不測の侵攻に対する早期警戒体制を構築する狙いがあります。
参加各国が保有する航空戦力を分担して投入することで、広範囲にわたる監視体制が形成されることが想定されています。とりわけ、継続的な空域監視が可能になることで、抑止力としての効果も一定程度期待されているようです。
黒海における機雷除去──航行安全と穀物輸出の確保
もうひとつの柱が、黒海における機雷除去作戦です。黒海では、ウクライナおよびロシア双方が自国沿岸の防衛を目的として機雷を敷設しており、さらに漂流機雷が第三国の領域にまで影響を及ぼす事例も見られています。
こうした状況に対応するため、有志国連合は機雷除去の実施方法として、以下のような複数の手段を想定しています。
- ルーマニアやトルコなどによる漂流機雷の発見と除去作業
- 掃海艦や掃海艇を用いた磁気・音響による掃海
- 水中無人機を用いた遠隔操作による機雷の切断と浮上処理
これらの手段が組み合わさることで、黒海の主要航路の安全が確保され、民間船舶の通行やウクライナからの穀物輸出が再開されやすくなると見込まれています。特に、国際的な食糧不安が広がる中で、黒海の安全な航行が果たす役割は小さくありません。
パリ常設本部とキーウ調整センターの連携体制
有志国連合はその運営拠点として、パリに常設本部を設置する方針を明らかにしています。この常設本部では、全体の戦略方針の策定や、参加国間の調整、資源の配分といった統括的な役割を担います。戦略と実務を結びつける中枢としての機能を持たせることで、効率的かつ統一的な意思決定が可能になると想定されています。
加えて、将来的にはウクライナの首都キーウに調整センターを設ける予定です。現地拠点として、ウクライナ政府や軍との緊密な連携を担い、地域の安全保障ニーズを把握しながら具体的な支援活動の調整を行うことが期待されています。補給や訓練支援など現場対応が求められる業務については、キーウの調整センターが前線拠点として柔軟に対応する構想が示されています。
このように、パリ本部が戦略的な意思決定と運営を司り、キーウが現地実務を担うという二層構造を整備することで、有志国連合としての統合的な機能発揮が図られようとしています。
第3章 英仏関係の再接近と欧州防衛の将来──不法移民・NATO改革・国際秩序の中で
欧州首脳の国賓訪問が示す外交的転換点
2025年7月、フランスのマクロン大統領が英国を国賓として訪問しました。これは、英国のEU離脱後初めてとなる欧州首脳による国賓訪問であり、象徴的な意味を持ちます。英国側としては、労働党のスターマー政権のもとでEUとの関係修復を外交政策の柱に据えており、マクロン大統領の訪問はその姿勢を国内外に示す格好となりました。
この訪問では、英議会での演説も行われ、「我々は多国間主義と国際秩序を守るために協力する必要がある」との訴えがなされました。とりわけ、ロシアのウクライナ侵攻や一部の政権が掲げる自国優先の外交方針を背景に、従来の国際秩序に対する挑戦が続いていることへの懸念がにじむ内容でした。
英EU関係の再構築に向けた具体的な動き
スターマー政権はEU首脳会議への参加を通じて、安全保障協定の提案を進めており、貿易や若者交流といった分野でも協力再開を模索しています。ドイツとの間では新たな2国間条約交渉も開始されており、防衛・経済の両面でより実務的な連携が試みられています。
ただし、貿易面では、英国が求める食品輸出入時の検査簡素化などについて、EU側が慎重な姿勢を崩していない点もあります。また、若者の移動の自由に関しても、移民に対する英国国内の世論を考慮し、柔軟な対応が難しいという事情もあるようです。こうした現実的な制約のなかで、粘り強い交渉が求められている状況です。
英仏が担う「欧州の防衛的責任」
イギリスとフランスは、欧州における唯一の核保有国であり、国連安全保障理事会の常任理事国でもあります。こうした立場を踏まえ、両国は「欧州の安全保障に対して特別な責任を負う」とする認識を共有しています。
マクロン大統領は「NATOに強力な欧州の柱を築く」と明言しており、アメリカの関与が相対的に薄れつつあるとされる現状において、欧州が主体的に防衛体制を強化していくべきだとの方針を明確にしています。この点においても、英仏の協調は重要な役割を果たすと見られています。
また、両首脳は巡航ミサイルの共同開発や合同部隊の拡大など、軍事的な実務面においても具体的な協力を進めています。核兵器の運用連携に加えて通常戦力でも連携を深めていくことは、欧州の防衛全体の実効性を高めるうえで不可欠といえるでしょう。
NATO改革と欧州主導の安全保障再構築
NATOは現在、国防費目標の引き上げに取り組んでいます。新たな指標として提示されているのが、GDP比5%を安全保障関連費に充てるというもので、内訳としては従来型の国防費を3.5%、有事に必要なインフラ整備など広義の安全保障分野に1.5%を充てる形が提案されています。
さらに、欧州連合(EU)は約8000億ユーロに及ぶ「再軍備計画」の推進に取り組んでおり、このうち1500億ユーロについては欧州債で調達する方針です。防衛産業の強化と共通装備の整備に向け、財政的裏付けを確保しながら欧州主導の防衛体制構築が目指されています。
フランスとポーランドは相互防衛条約を締結しており、アメリカのプレゼンスが不確実な中、地域的な安全保障枠組みの補完を進める姿勢も見られます。フランスとしては、自国の核戦力の抑止対象を欧州の同盟国に拡大する構想も示されており、これも欧州自立の一環として注目されています。
不法移民問題と英仏の対応スキーム
英仏両国は、急増する不法移民問題に対しても協力を強化しています。両国は、英仏海峡を渡って不法に入国した者をフランスに送還し、難民申請が正当と認定された移民については英国が同数を受け入れるという相互バランス型の送還スキームに合意しました。
ただし、この制度が実際にどこまで機能するかについては不透明な部分も残されています。過去には英国が計画した移民の第三国移送制度が頓挫した経緯もあり、新たな枠組みが制度として安定的に運用されるためには、実務面での制度整備と世論の理解が不可欠となるでしょう。
欧州の防衛と米国との距離感のバランス
欧州が自立した防衛体制を模索する一方で、従来から続く米国との「特別な関係」への影響にも配慮が求められています。特に米国が、EUの防衛産業優遇策に対して懐疑的な立場を示す可能性がある中で、英仏がどのように多国間主義を維持しながら大西洋同盟を調整していくかが問われています。
こうした文脈では、外交・防衛をめぐる戦略的バランスがより複雑になっており、英仏のリーダーシップが欧州全体の安全保障の舵取りにどのように機能するのかが今後の焦点となりそうです。
免責事項
本記事は、公開時点の報道情報に基づいて作成されています。
記載された政策・枠組みの内容は変更される可能性があるため、実務での判断にあたっては最新の公式情報をご確認ください。
また、記事内では特定の企業・組織・サービスに関する推奨・評価は行っておらず、個別の投資・外交判断を目的としたものではありません。
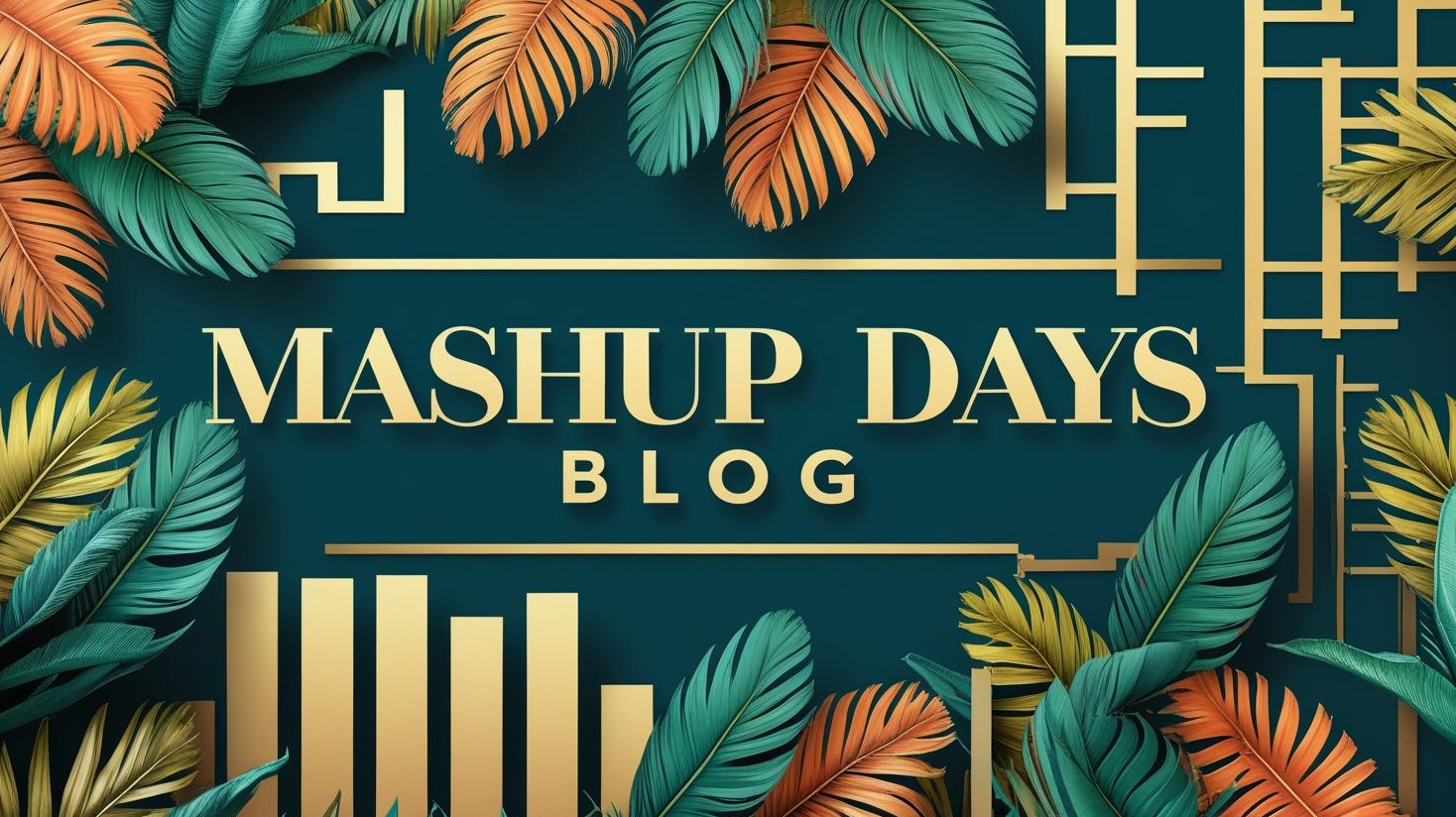








コメント