第1章 買収撤回が映すセブン&アイのガバナンス転換点
1‑1 ACTによる買収提案──1年越しの交渉が迎えた終止符
カナダの流通大手アリマンタシオン・クシュタール(ACT)は、2024年夏から約1年にわたり、セブン&アイ・ホールディングス(以下、セブン)に対して買収提案を行ってきました。
提示された条件は、1株あたり18.19ドル(約2,600円)、総額で約7兆円。
2025年5月には、両社が秘密保持契約(NDA)を締結し、米国での店舗売却を含む協議に進展が見られたものの、7月16日にACTは「セブンから建設的な協議が見られない」として提案を撤回しました。

1年近くにわたる交渉の末、買収提案が幕引きとなった背景には、双方の交渉姿勢のすれ違いがあったようです。
M&Aでは、価格以上に『信頼』が鍵となります。
1‑2 秘密保持契約(NDA)のポイントと協議の壁
ACTとセブンの間で締結されたNDA(秘密保持契約)には、開示情報の定義、使用範囲の限定、契約期間、損害賠償、敵対的買収の禁止などが盛り込まれていました。
ACTは、より踏み込んだ情報開示を求めていましたが、セブンは慎重な姿勢を崩さず、その溝が埋まることはありませんでした。
💬 用語解説:NDA(秘密保持契約)
M&A交渉などで、相手方に対して開示された企業情報を第三者に漏らさないよう義務付ける契約。



NDAは、M&Aにおける前提条件です。
文面の堅牢さだけでなく、情報開示への誠意ある姿勢が問われる局面でした。
1‑3 アクティビストの要求とセブンの経営刷新
セブンは2023年、アクティビスト(物言う株主)である米バリューアクト・キャピタルと対立。
コンビニ事業への集中と構造改革を求める提案を受け、非コンビニ事業の売却や経営陣の刷新に踏み切りました。
2024年秋には創業家主導で非公開化案も浮上しましたが、最終的には取り下げられ、2025年3月には社外取締役のスティーブン・ヘイズ・デイカス氏が新社長に就任しています。
💬 用語解説:アクティビスト株主
経営効率や資本政策の改善を目的に、企業に対して積極的に提案や要求を行う株主。



アクティビストの存在は、企業にとって時に厳しい要求を伴いますが、結果的にガバナンスの透明化や経営の俊敏化を促す原動力にもなり得ます。
1‑4 株価急落──市場の反応はシビアだった
ACTによる買収提案撤回が発表された翌日の東京市場では、セブンの株価が一時10%下落(前日比212円50銭安の1,997円50銭)。
終値でも9%安の2,007円を記録しました。市場では、買収によるプレミアム(上乗せ期待)が剥落し、セブン単独での成長シナリオに懸念が広がった形です。
💬 用語解説:プレミアム
M&Aにおいて、買収価格が市場株価を上回ることで株主にもたらされる追加的な価値。



市場は“幻のM&A”に冷静でした。
買収プレミアムが消えた以上、単独成長の明確なビジョンが求められます。
1‑5 米独禁法が生む足かせ──M&A交渉に潜むもう一つの壁
ACTとセブンの協議では、米国市場における店舗売却が重要な争点となっていました。
米国内で両社の店舗が約2,000店舗重複しており、独占禁止法に抵触する可能性があったため、この重複する店舗について事前に売却交渉が進められていたのです。
このように、米国におけるM&Aでは、当局の審査と承認プロセスが企業の戦略に大きな影響を与えることもあります。
💬 用語解説:独占禁止法(反トラスト法)
企業による市場の支配や寡占状態を防ぎ、公正な競争環境を保つために施行されている法律。



グローバルM&Aでは、競争法の壁をいかに越えるかが成否を分けることも。特に米国の規制は慎重な対応が求められます。
企業買収という重大な選択肢が消えた今、セブンには単独路線での成長戦略と、その実行力が強く問われています。
外部の圧力をガバナンス強化のチャンスととらえられるか。
その答えが、企業価値の行方を左右することになりそうです。
第2章 国内外コンビニ事業の課題とセブン&アイの再構築戦略
2‑1 価格戦略の転換点──「うれしい値!」と高付加価値商品の両立
セブン&アイは、物価上昇や消費者の節約志向の高まりを受け、2024年秋から低価格シリーズ「うれしい値!」を展開しました。おにぎり・菓子・飲料など約270品目を対象に、価格のハードルを下げることで来店頻度の回復を狙いましたが、収益面では商品粗利益率の低下が足かせとなりました。
そこで2025年以降は、紅茶や焼き菓子など付加価値を備えた商品の比重を高め、低価格戦略と高収益商品の“二軸構成”で収益性の改善に挑んでいます。
💬 用語解説:商品粗利益率
商品の売上高に対する粗利益(売上総利益)の割合。価格とコストのバランスを示す収益性の指標。



価格を下げれば客足は増えますが、粗利を守るには“選ばれる商品”が不可欠。
今は“安さ”だけでなく“満足感”を売る時代ですね。
2‑2 競合が仕掛ける差別化──ローソンとファミリーマートの戦略
6月の既存店売上データをみると、ローソンが前年同月比7.7%増、ファミリーマートが4.4%増と、いずれもセブンを上回る成長を見せました。
ローソンは約50%の増量キャンペーンを実施し、ファミリーマートは人気選手の広告起用による話題性で消費者の関心を集めました。
平均日販(1日あたりの店舗売上)は、ローソン・ファミリーマートともに約57万円と、セブンの約69万円にまだ及びませんが、各社とも「既存店の磨き込み」に本腰を入れてきており、競争は次のフェーズに入っています。
💬 用語解説:既存店売上高
過去1年以上営業している店舗の売上高を集計し、前年同月と比較することで成長度合いを測る指標。



競合の戦い方を見ると、単なる価格勝負ではなく“体験価値”や“ブランド連携”で勝負する流れに変わってきています。
2‑3 低価格戦略の落とし穴──業態間競争の激化
セブンが低価格商品を強化したことで、必然的に競合の裾野は広がり、ドラッグストアやディスカウントストアと同じ土俵での戦いが避けられなくなりました。
これら業態は食品・日用品の大量展開と低コストオペレーションを武器に、価格志向の顧客を吸収しています。
こうした中で、セブンが求められるのは“価格競争”のその先です。
単に「安い」だけではなく、「ここにしかない価値」で選ばれる存在になれるか。
収益性を守りながら顧客満足を引き上げる難易度の高い舵取りが続きます。
💬 用語解説:低価格戦略
他社よりも安価な価格を設定することで、来店動機や購入意欲を高め、集客を図るマーケティング手法。



低価格を追求するあまり、気づけば“価格でしか選ばれない店”になってしまうケースも。
今は“安くて、いい”をどう作れるかが鍵です。
2‑4 新業態「SIPストア」──コンビニとスーパーの融合モデル
セブンは新たな一手として、コンビニと食品スーパーを組み合わせた新型業態「SIPストア」を千葉県松戸市にオープンしました。この店舗は、従来型コンビニの約2倍にあたる約290㎡の売場面積と5,300品目以上の商品数を誇ります。
注力ポイントは、野菜・精肉・冷凍食品などの生鮮品の拡充と、レジ横で提供される揚げたカレーパンや焼き菓子、スムージーといった店内調理のファストフード。
価格はコンビニ水準を維持しつつ、スーパー並みの品ぞろえを兼ね備えた“いいとこ取り”のモデルです。
ターゲットは、在宅勤務や高齢化が進む住宅街の生活者。
必要なものを近場で効率よく買いたいというニーズに応える形で、1日あたりの売上目標は130万円超を見込んでいます。
💬 用語解説:ビジネスモデル
商品やサービスを通じて、どのように利益を創出するかという事業の基本構造のこと。



コンビニにスーパーの利便性を融合させるという発想は、まさに生活の変化を捉えた戦略ですね。今後の出店拡大に期待がかかります。
2‑5 北米市場の現状と再建への布石
セブンの北米事業は、2025年3〜5月期においてドルベース売上は6%減、既存店売上は1%減となり、苦戦が続いています。
都市部に多くの店舗を持つことから、中低所得者層の消費落ち込みが直撃した形です。
これに対しセブンは、不採算店舗約440店の閉鎖を2026年までに完了させる方針を掲げ、商品構成の見直しも強化。日本で成功した店内調理商品やPB(プライベートブランド)を北米でも展開し、収益性の向上を狙います。
また、2026年下半期には、米国子会社のIPO(新規株式公開)を通じて資金を調達し、成長投資と株主還元のバランスを取る計画です。
💬 用語解説:PB(プライベートブランド)
小売業者が独自に企画・開発して販売する商品。
価格と収益性のバランスに優れるため、差別化戦略の柱となることが多い。



北米では“コストを削るだけ”では限界があります。
“何を強みにするか”を明確にした再成長プランが求められています。
国内市場では価格と価値の再定義、海外市場では回復と再投資の両立。
セブン&アイの戦いは“いまある店をどう磨き上げるか”にかかっています。
競争環境の変化に向き合いながら、次の成長モデルをどう描けるか──その答えは、日々の現場での積み重ねに表れはじめています。
第3章 2030年に向けた成長戦略とセブン&アイの資本政策
3‑1 中期経営計画の柱──売上30兆円をどう実現するか
セブン&アイは、2030年度までにグループ売上高を30兆円へ拡大する目標を掲げています。
これは、2024年度比で約63%増となる大幅な成長計画であり、実現には国内外の事業基盤強化と新たな成長投資が不可欠です。
その原動力として、設備投資およびM&Aに約3兆円を投じる方針が示されており、今後の出店戦略・業態転換・海外展開などを通じて、数値目標(KPI)との整合性が注目されています。
💬 用語解説:KPI(重要業績評価指標)
目標達成度を数値で測るための指標。経営戦略の進捗管理に用いられる。



売上30兆円という数字だけが独り歩きしないように、投資の質や施策の中身が問われます。
どの分野で、どう成長するか──その絵が大切です。
3‑2 北米子会社のIPO──上場と資金調達のバランス
セブンは、北米のコンビニ子会社(セブン-イレブン・インク)の新規株式公開(IPO)を2026年下半期までに実施する計画を維持しています。企業価値は5兆円規模とみられ、IPOによって得られる資金は、株主還元と成長投資の原資として活用される見通しです。
上場タイミングは、北米市場の景況感や投資家の需給状況も踏まえつつ柔軟に調整されるとみられ、市場との対話姿勢も注視されています。
💬 用語解説:IPO(新規株式公開)
株式を証券取引所に上場し、一般投資家に広く販売できるようにすること。
資金調達や企業価値の可視化に用いられる。



IPOは単なる資金調達の場ではなく、その企業の次の成長戦略の意思表明でもあります。
市場に何を語れるかが、問われる局面です。
3‑3 ROEの改善──資本効率を取り戻すために
一方で、セブンの自己資本利益率(ROE)は近年低下傾向にあります。
18年2月期と比較すると、時価総額は約4割増加しているものの、ROEは3ポイント超下落。
背景には、国内コンビニ事業の苦戦、米国コンビニ事業の不振、不採算事業の整理損失などが挙げられます。
この課題に対し、セブンはコンビニ事業への集中、スーパー事業の改革、北米IPOなど、複数の打ち手を同時進行で講じています。
💬 用語解説:ROE(自己資本利益率)
純利益を自己資本で割った指標。投資家にとっては資本効率の良さを測る重要な数値。



ROEは“稼ぐ力”と“資本の使い方”の両方を映す鏡。
見せかけでなく、本業の持続的収益力を高めてこそ、数値に表れます。
3‑4 2兆円の自社株買い──株主還元と企業評価の両立
セブン&アイは、2030年度末までに総額2兆円の自社株買いを実施する方針です。
この規模の自社株買いは、1株あたり利益(EPS)の押し上げやROEの改善、また市場に対する「株価が割安である」とのシグナリング効果が期待されます。
実際、過去には自社株買いの発表により短期的な株価上昇が確認されたケースもあります。
ただし、成長投資とのバランスが伴わなければ、市場は評価しづらい面もあるため、還元と成長の両立がより重視されています。
💬 用語解説:自社株買い
企業が市場から自社株を買い戻すこと。
発行株数の減少により1株当たりの価値が上がり、株主への還元策として用いられる。



株を買うだけで価値が上がるわけではありません。
企業として何に投資し、何を伸ばすのかを一緒に語ることが重要です。
国内での磨き上げと、海外での挑戦。セブン&アイの2030年ビジョンは、ただの数字ではなく、今、どの選択をするかの積み重ねによって実現されていくものです。
資本政策も、成長戦略も、企業としての覚悟が問われるステージに入っています。
免責事項
本記事は公開時点の情報に基づいて作成されていますが、最終的なご判断は必ず公式発表や一次情報をご確認のうえ行ってください。
本記事の内容に基づいて生じたいかなる損害についても、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。








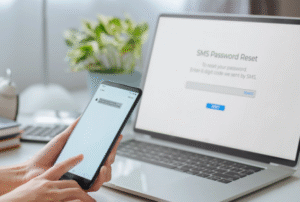
コメント