英検を受けたいけれど「本会場が遠い」「日程が合わない」「費用が気になる」
そんなお悩みをお持ちの方へ。
実は、英検には学校や塾などで受験できる「準会場」という選択肢があります。
受験料が抑えられ、慣れた環境で試験を受けられるなどメリットも豊富。
この記事では、準会場の仕組みから探し方、申込の流れ、当日の注意点、効率的な学習法までをわかりやすくまとめました。
英検受験をより自分らしく、無理なく進めたい方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
第1章|英検準会場の仕組みと制度の背景
英検準会場とは?その成り立ちと役割を知ろう
英検の準会場制度は、1970年に第3回検定の4級で学校内受験が初めて実施されたことからスタートしました。
当時は年2回の実施にとどまっていた英検ですが、「もっと受験のチャンスを増やしてほしい」という現場の声を受け、年3回体制への移行を目的として制度が導入されました。
その後も制度は段階的に拡充されていきます。
たとえば1991年には「中学・高校特別準会場」が創設され、学校での土曜日実施が可能に。
2002年には金曜日の実施も追加され、週5日制に対応。
さらに2021年には、一次試験の日程を複数週に分散できる制度改革が実現し、申込団体の都合に合わせた柔軟な運用が可能になりました。
準会場制度は、学校や塾など現場のニーズに応えながら発展してきた制度だと言えるでしょう。

制度の背景を知ると、準会場が妥協策ではなく必要とされて育ってきた制度だということがよくわかりますね。制度の信頼性にもつながります
準会場と公式会場の違いを整理する
英検は、同じ試験でも「公式会場(本会場)」と「準会場」という2つの受験スタイルから選ぶことができます。
ここでは、両者の違いを整理しておきましょう。
| 比較項目 | 公式会場 | 準会場 |
| 受験料 | 例2級 9,100円 | 例2級 6,900円(約24%割引) |
| 会場 | 協会指定(遠方になることも) | 所属団体または近隣の塾・学校など |
| 受験可能な級 | 1級~5級 | 2級~5級(1級・準1級は不可) |
| 二次試験 | 一次・二次ともに同系列会場 | 二次試験は本会場で受験が必要 |
このように、費用と利便性では準会場に大きなメリットがある一方で、級や会場の自由度では一部制約もあります。



特に2級以下の受験者にとって、準会場はコストパフォーマンスとアクセス性のバランスが非常に良い選択肢です
受験者が感じているメリットと心理的な安心感
準会場を選ぶ人が特に評価しているのは、経済的な負担の軽さと、慣れた場所で安心して受験できる点です。
- 検定料の差:たとえば2級では約2,200円、5級では約1,600円も安くなります。
- 環境面の安心感:「いつもの学校や塾」で、「知っている先生の前」で受けられることにより、緊張がやわらぐという声が多くあります。
- 待ち時間が少ない:小規模会場のため集合から試験開始までの待機時間が短く、スムーズな進行が期待できます。
このようなメリットに魅力を感じて、特に中高生や小学生の受験者、またその保護者から高い支持を集めているのが準会場です。



慣れた教室、知っている先生、顔見知りの友人と受ける環境が、子どもの集中力やリラックスにも大きく影響します
教職員への負担と現場のリアル
一方で、準会場を運営する学校や塾にとっては、その裏で大きな準備負担が発生していることも事実です。
- 教室割り・座席配置の事前準備
- 申込受付や検定料の集金など事務処理
- 休日出勤による精神的・肉体的なプレッシャー
- 申込ミスやトラブル対応への責任の偏り
特に、「英語科教員だけに業務が集中している」といった声も少なくなく、場合によっては働き方改革の一環として準会場の開催を一時中止した学校もあるようです。
ただし、そうした状況でも保護者からの「全員受験してほしい」という要望を受けて再開するケースもあり、再開時には委員会を設けて校内全体で負担を分散する取り組みが行われています。



準会場制度が継続できているのは、現場の先生方の献身的な支えがあってこそ。その現実にも目を向ける必要がありますね
制度の未来|選ぶ側も、支える側も納得できる形へ
準会場制度は、当初は受験機会の拡大を目指すものでしたが、今では費用・利便・心理面で多くの受験者に選ばれる制度にまで成長しました。
とはいえ、支える現場の負担という課題もあります。
今後は、受験者にとって安心・安全な受験環境であることはもちろん、運営する学校や塾にとっても無理のない体制が整えられることが重要です。



準会場は受けやすい英検を支える重要な仕組みです。利用する側もその背景を知って、感謝と配慮を持って臨みたいですね
※次章では、準会場を実際に利用するための「探し方」や「申込方法」「費用比較」について、さらに具体的に解説していきます。どこで、どうやって、どんな準備が必要なのか。しっかり把握していきましょう。
第2章|英検準会場の探し方・申込フロー・費用比較
英検準会場は選べる?探し方のコツと注意点
英検の準会場は、自分で会場を選べるケースも多く、受験スタイルに合わせた柔軟な選択ができるのが特徴です。
ただし、その仕組みは少し複雑で、タイミングや地域によっては選択肢が限られる場合もあります。
準会場は、主に学校や塾などの団体が会場となっており、中には外部の一般受験者を受け入れている団体も存在します。英検協会は、都道府県ごとに「一般受験者受け入れ団体一覧」を公式サイトで公開していますが、情報の掲載は受付期間中に限られるという点には注意が必要です。
また、リストに掲載されていない塾や学校でも、実際には受け入れているケースもあります。
そのため、準会場を探す際は、公式情報に加えて、地域の塾に直接問い合わせるなどの能動的なリサーチも重要になります。



公式サイトだけで探すと見つからない会場もあります。
地域の大手塾や英語教室に一度連絡してみるのも有効ですよ
準会場の申込手順を時系列で確認しよう
準会場での英検受験は、団体側が中心となって手続きを行います。
受験者自身が動く本会場とは違い、団体経由の申し込みには独自のフローがあるため、早めの把握が大切です。
以下は、主に塾などの準会場運営団体で行われる申込手順の流れです。
① 団体登録と資材の取り寄せ
塾などが準会場として試験を実施するには、まず英検協会へ団体登録(3年更新)と準会場登録が必要です。
登録が完了したら、申込書や受験案内などの資材を取り寄せて準備を整えます。
② 受験申込と検定料の支払い
受験者(または保護者)は、塾の案内に従って申込用紙を提出し、検定料を塾に納めるか、個人で支払う形になります。団体はこれを取りまとめて、一括払込または個人払いで協会に支払う方式を選択可能です。
③ 受験票代わりのリスト管理
準会場では、本会場のようなハガキ型の受験票は発行されません。
代わりに、団体内で名簿を管理し、当日は名簿と本人確認資料で照合が行われます。
④ 試験資材の受領と実施
団体には、協会から問題冊子、解答用紙、監督マニュアルなどの一式が送付されます。
当日は、この資材を用いて、団体の教室などで試験を実施します。



準会場で受けるからといって手抜きな運営は一切ありません。
むしろ、運営者側はかなり入念な準備をしていますよ
申込締切と救済措置|うっかりミスはNG
英検の申込締切は非常に厳格であり、原則として締切後の申込は一切受け付けられません。
保護者がうっかり見落としてしまった場合でも、理由を問わず受付不可という対応が基本です。
ただし、まれに申込期間が数日延長されることがあります。
そうした場合には、公式サイトに記載される最新情報をこまめにチェックすることで、救済のチャンスが得られることもあります。
また、締切に間に合わなかった際は、別日程の試験(英検S-CBTやS-Interviewなど)を検討することもひとつの手段として案内されています。



あとで探せばいいやでは遅いことが多いです。
カレンダー登録やリマインダーで締切日を管理しておきましょう
英検準会場と本会場の検定料を徹底比較
英検を受験する際に気になるのが、やはり受験料の違いです。
準会場と本会場では費用に明確な差があり、級によっては1,000円以上の割引になるケースもあります。
| 級 | 本会場 | 準会場 | 割引率 |
| 2級 | 9,100円 | 6,900円 | 約24%引き |
| 準2級 | 8,500円 | 6,100円 | 約28%引き |
| 3級 | 6,900円 | 5,000円 | 約27.5%引き |
| 4級 | 4,700円 | 2,900円 | 約38.3%引き |
| 5級 | 4,100円 | 2,500円 | 約39.0%引き |
受験級が低くなるほど割引率が大きくなる傾向にあり、複数級を連続して受ける受験生には特に大きな恩恵があります。



この価格差は見逃せません。
1回の試験ごとに数千円節約できるなら、その分を教材やレッスンに回すこともできますね
支払方法と手数料の最新事情
準会場では、検定料の支払い方法として以下の2種類が選べます。
- 団体一括払い:塾や学校が生徒から集金し、まとめて協会に支払う方式。
- 個人払い:生徒が自分でコンビニ払いやクレジットカードで支払う方式(団体ポータル利用時限定)。
支払い方法によって手数料の負担者も異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
| 支払手段 | 手数料の扱い |
| 郵便払込(団体) | 協会が手数料負担 |
| 銀行振込(団体) | 団体側の負担 |
| コンビニ払い(個人) | 数百円の手数料が受験者負担 |
| クレジット払い(個人) | 手数料無料のケースが多い |
最近は、教職員の負担軽減を目的として個人払い方式を採用する団体も増えており、オンラインでの支払い対応も進んでいます。



個人払いは便利な反面、受験者自身に支払責任があるので、リマインダー設定や親のサポートは必須です
地方受験者が直面する課題と対応策
地方では、本会場が遠方にしかない、外部受験者を受け入れる準会場が少ないなど、会場選びに苦労する声が多くあります。ある受験者は、「本会場が日曜で都合が合わず、準会場を探して片っ端から電話をかけた」というエピソードを語っています。
こうした状況では、以下のような工夫が有効です。
- 隣県の準会場も視野に入れる(協会サイトでは県境をまたいで検索可能)
- 締切前に、前週や土曜実施の会場を狙って早めにリサーチする
- SNSや口コミを活用して非公開の会場情報を得る
準会場は全国に多数ありますが、その中で「自分が申し込める会場」を見つけるには、情報収集の姿勢が重要です。



地方にお住まいの方は、情報の速さと深さが勝負です。
受験チャンスを逃さないよう、早めの行動を心がけましょう
※次章では、試験当日の流れや持ち物、忘れ物・遅刻・設備環境の注意点まで、受験を成功に導くための具体的な準備ポイントを詳しく解説していきます。
準会場の特性を理解し、安心して試験当日を迎えるための知識をここで整理しておきましょう。
第3章|英検準会場の当日流れとトラブル防止マニュアル
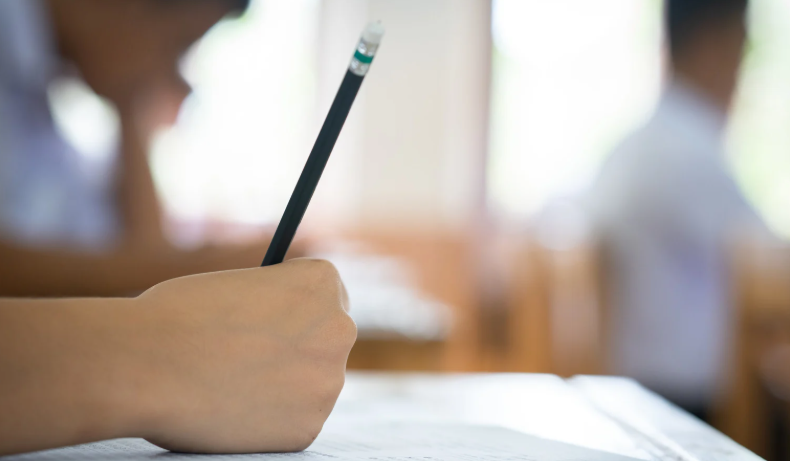
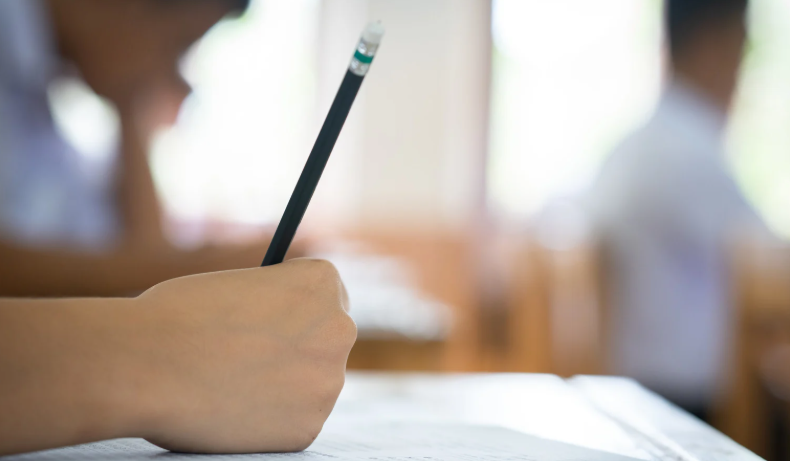
試験当日のスケジュールと準会場ならではの特徴
英検準会場での試験当日は、スムーズに進行するよう細かく運営されています。
流れ自体は本会場と似ていますが、会場規模や設備、スタッフの構成によって異なる点もあるため、あらかじめ全体像を把握しておくことが大切です。
おおまかなタイムラインは以下のとおりです。
| 時間帯 | 会場側の運営 | 受験者の行動ポイント |
| 開場前 | 教室レイアウト・掲示物確認 | 時間に余裕を持って現地到着 |
| 受付 | 本人確認と名簿照合 | 必要書類を持って静かに入室 |
| 試験直前 | 注意事項の読み上げ | 筆記用具を確認し心を整える |
| 試験中 | 時間管理・不正監視 | 指示に従い静かに受験 |
| 試験終了 | 問題・解答用紙の回収 | 私物を忘れず退室 |
準会場ではハガキ型の受験票がない代わりに名簿での確認が行われます。
試験監督は教室内で、受験番号や顔確認・注意事項のアナウンス・試験中の監視・答案の回収と封入までを担当します。



準会場でも、英検協会の監督マニュアルに従って本会場と同じレベルで運営されています。安心して試験に臨んで大丈夫です
英検準会場で忘れやすい持ち物とチェックポイント
試験当日に意外と多いのが忘れ物による焦りやトラブルです。
筆記用具はもちろん、準会場ならではの注意点も含めて、事前に準備しておきたい持ち物をまとめておきましょう。
よくある忘れ物
- 鉛筆・消しゴム・腕時計(音の鳴らないアナログ式)
- 上履き(スリッパ)特に学校の教室を使用する場合は必須
- コンビニ払込控えなどの受験情報団体申込でも自分の級や受験番号の控えを持っておくと安心
特に小学生や初受験者の場合、机や椅子の高さが合わず落ち着かないということもあるので、足置き台や座布団の準備もひとつの対策になります。



準会場では、うっかり上履きを忘れて靴下で受ける子もいます。
小さな備えが本番の安心感につながりますよ
遅刻・体調不良時のルールは非常に厳格
英検は、公平性を重視した試験であるため、遅刻や欠席に関しても明確な基準が設けられています。
特に準会場では、運営側も決められた手順に沿って動くため、受験者側もルールをしっかり理解しておくことが求められます。
遅刻の基準(一次試験)
- 4・5級開始から15分以内の入室まで受験可能
- 3級以上開始から30分以内であれば入室可
※それを過ぎると、理由の如何にかかわらず受験不可となります。
また、たとえ入室が許されたとしても、延長措置は一切なく、残り時間で解答する形になります。
体調不良・欠席の場合
- 感染症や急な体調不良があっても、原則として振替や返金は不可です。
- 試験会場で発熱が確認された場合は、入場を断られることもあります。



時間に遅れると残り時間での受験になるため、不利になる可能性があります。必ず余裕を持って到着を心がけましょう
準会場特有の環境と設備制約に注意しよう
準会場は、塾や学校の教室をそのまま使うことが多いため、本会場とは異なる環境になることがあります。
知っておくと安心できるポイントをいくつかご紹介します。
座席配置とスペースの違い
- 小規模な教室では、受験者同士の距離が近くなることも
- 教室によっては1席おきやジグザグ配置で工夫されている
椅子と机の高さ
- 小学生が中学校の椅子を使用する場合など、足が届かないと集中力に影響することもあります
- 足置きやクッションなどでの調整がおすすめです
音響環境
- 校内スピーカーやポータブルCD再生機を使用
- 部活動やチャイムの音、外部の声などが影響する可能性もあるため、遮音の工夫がされていることが多いです
会場の備品や掲示物
- 試験に関係のある掲示物(英単語ポスターなど)は、事前に取り外されるか隠される対応が取られます



設備は本会場のように整っていないこともあるため、事前にこういう環境かもと予想しておくと当日慌てずに済みます
緊張を和らげる工夫と現場のあたたかい雰囲気
英検の本番は、多くの受験者にとって緊張の瞬間です。
特に準会場は身近な場所で実施されるとはいえ、独特の緊張感があるのも事実です。
そこで、現場ではさまざまな緊張緩和の取り組みが行われています。
監督者のひと声が効果的
- 「リラックスしてくださいね」「落ち着いて大丈夫ですよ」といった声かけが、受験者の表情を和らげることがあります
- 試験官がにこやかに接するだけでも安心感が生まれます
BGMの活用
- 一部の準会場では、試験前の待ち時間にクラシック音楽などを流して緊張をやわらげる工夫がされています
他の受験者との空気感
- 同じ教室で受ける仲間の存在が、心理的な安心感や連帯感を生むことも
- 軽く会話を交わすだけでも気持ちがほぐれるという声もあります



試験=ピリピリした空間というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、準会場ではあたたかみのある空気が流れていることも多いんですよ
※次章では、英検準会場での受験をさらに実りあるものにするために、短期間で成果を出すための学習ハックや、スキマ時間の活用術、効果的な教材選びなど、学習フェーズにフォーカスしたノウハウをお届けしていきます。
準会場という環境を最大限に生かすための工夫を、ここでしっかり押さえておきましょう。
第4章|英検準会場を最大活用する学習ハックと時間術
短期間で結果を出す人の学習時間配分を知る
英検の合格に向けて「どのくらいの時間を、どんなふうに使えばいいの?」という疑問を持つ方は多いかもしれません。実際に短期間で合格を果たした人たちは、それぞれの生活スタイルに合わせて戦略的に学習時間を確保しています。
合格者3人のリアルな時間設計
| 受験者 | 合格級 | 学習期間 | 学習時間の使い方 |
| 大学生A | 英検2級 | 2か月 | 平日通学中に1時間リスニング、夜に筆記演習/週末は3〜4時間まとめて過去問演習 |
| 高校生B | 準2級 | 1か月 | 平日2時間×5日+土日5時間ずつ。毎週過去問と作文・リスニングを交互に集中練習 |
| 社会人C | 準1級 | 3週間 | 通勤中にシャドーイング、昼に長文読解、夜は過去問演習。週末は模試形式で演習と復習を繰り返す |
短期間で合格する方は前提の知識の差はありますが、自身の知識レベルに合わせて単語・過去問・弱点補強のバランスが取れた計画的な配分をしているという点で共通しています。
特に通勤や通学、昼休みなどのスキマ時間をうまく使っている点が印象的です。



最初に何週間で合格するかという期限を決めると、学習時間の配分にもメリハリがつきますよ
シャドーイングを使ったリスニング強化法
英検対策でリスニングが苦手な人には、シャドーイングというトレーニング法が非常に効果的です。
音声を聞いてすぐに真似して発話するこの方法は、聞き取る力と発音の意識を同時に鍛えられるため、特に短期集中型の学習に向いています。
レベル別おすすめ教材
| レベル | 教材名 | 特徴 |
| 初級 | NHK基礎英語/エンジョイ・シンプル・イングリッシュ | ゆっくりした音声とスクリプト付きで、初心者も安心 |
| 中級 | VOA Learning English/速読速聴・英単語シリーズ | 平易なニュース英語と語彙強化が両立できる構成 |
| 上級 | TED Talks/Audible英語教材 | ネイティブの自然なスピードに触れられる実践向き素材 |
「ちょっと簡単すぎるかも?」と感じるレベルから始めるのがコツ。
成功事例では、1日15〜30分のシャドーイングを3ヶ月継続し、リスニング満点近くまで到達したケースもあります。



音を真似るだけでなく、なりたい声のモデルを決めるとモチベーションも上がります
社会人でも続くスキマ時間活用法
「まとまった勉強時間がとれない…」と悩んでいる方でも、隙間時間をうまく活用すれば、しっかり学習量を確保できます。むしろ、スキマ時間だからこそ、習慣として継続しやすいというメリットも。
成功者のスケジュール例
- 製薬会社勤務の男性(準1級合格)
通勤電車で単語→昼休みに英会話アプリ→夜に過去問の復習
→ 合計1日3時間を分散して学習 - 商社勤務の女性(2級合格)
朝の15分でシャドーイング、昼の15分で単語アプリ、帰宅途中の電車15分で復習
→ 1日45分を3回に分ける学習で継続性アップ - 英語学習コミュニティ参加の会社員
勉強記録を毎日投稿し合う仕組みで、半年間継続&準1級合格
→ 仲間との共有が継続の原動力に



まとまった時間がない人こそ、15分×3回のように細切れで学ぶと習慣化しやすいですよ
準会場×オンライン英会話の併用が効果的
準会場で一次試験を受ける人にとって、スピーキング対策の不足はよくある悩みです。
そんなときにおすすめなのが、オンライン英会話との併用。
特に二次試験(面接)の直前期に活用すると、大きな成果が出やすくなります。
実際の利用者の声
- 高校生Dさん(2級合格)
塾で一次対策、週2回のオンライン英会話で面接練習
→ 本番で緊張せずA判定獲得 - 社会人Eさん(準1級合格)
毎日25分のオンラインレッスンを3ヶ月継続
→ リスニング満点近くまで伸びたとの自己分析あり - 費用対効果の工夫
準会場の割安な受験料を活用し、浮いた分をオンラインレッスンに回す
→ 時間と費用をバランスよく配分できる手段として注目



リスニング強化にも話す練習にも、オンライン英会話は本当に有効です。1回25分でも積み上がれば大きな力になりますよ
学習コミュニティでモチベーションを維持する
英語学習は長期戦になりがちで、途中で挫折してしまう人も少なくありません。
そんなとき、仲間と励まし合える学習コミュニティの存在が大きな支えになります。
よくあるコミュニティのメリット
- 目標を共有してモチベーションを刺激
→ 仲間と「来月の受験までに単語帳1冊」など目標設定をするとやる気が継続 - 情報共有で学習効率アップ
→ 他の人が使っている教材を知ったり、自分に合った学習法が見つかるきっかけになる - 教え合い効果で理解が深まる
→ 誰かに説明することで、自分の知識もより定着しやすくなる - 孤独感の解消
→ 英語学習が「ひとりの戦い」ではなくなり、継続がラクになる
あるアンケートでは、学習コミュニティ参加者は非参加者より平均学習時間が30%以上多かったという結果も出ています。



学習の継続には、外発的な刺激も大切。
仲間と一緒に学べる環境があると、自然と前に進めます
※ここまで、英検準会場の活用を最大化するための学習方法と習慣化のコツをご紹介しました。
次章ではいよいよ、読者の方が次の一歩を踏み出すためのおすすめ学習サービスと選び方のヒントをご案内します。
具体的な行動に移すためのきっかけとして、ぜひ最後までチェックしてみてください。
第5章|英検準会場の学びを次のステップにつなげるために
この記事を読んで、英検準会場の活用方法や学習の進め方が少しクリアになった方もいらっしゃるかもしれません。
「よし、実際に一歩踏み出してみようかな」と感じた方のために、ここでは学習の質をさらに高めるための参考サービスを3つだけ、厳選してご紹介します。
ご自身の目的やスタイルに合った学びを見つけるための、ひとつのヒントになれば幸いです。



このサービスを絶対に使ってほしいということではありません。
あくまで次の選択肢を探すヒントになればうれしいです。皆様の行動を後押しするきっかけになればと思います
英語4技能を一気に伸ばしたい方へ
【アルプロス】短期集中型の英語スクール
- 海外の語学学校と同じカリキュラム
- 英語で考えられるようになる本格トレーニング
- TOEFL・IELTS・英検にも対応
- ビジネス英語や留学準備まで幅広くカバー
最短1ヶ月で英語脳をつくる環境を探している方にぴったりです。
▼ 詳細は以下をクリックして公式サイトをご確認ください(PR)



本気で伸ばしたいとき、環境を変えるのも大事な選択肢のひとつです
リスニングに特化して効率を高めたい方へ
【シャドテン】シャドーイング特化型学習サービス
- 毎日プロからフィードバックが届く
- 教材はレベル別に自動提案
- アプリひとつで完結、7日間の無料体験あり
音の変化に強くなりたい方、面接対策にもリスニングを活かしたい方におすすめです。
▼ 詳細は以下をクリックして公式サイトをご確認ください(PR)



聞こえないを聞き取れるに変えるには、やっぱり正しい方法と毎日の積み重ねがカギです
英語をもっと気軽にアウトプットしたい方へ
【LanCul】英会話カフェで楽しく実践
- レッスンではなく、カフェでリアルな会話
- 全国25店舗+オンラインもOK
- 初心者にもやさしい雰囲気、無料体験あり
準会場での試験対策に加え、日常の中で英語で話す感覚を身につけたい方に向いています。
▼ 詳細は以下をクリックして公式サイトをご確認ください(PR)



英語で話すこと自体が怖くなくなれば、面接も自然に乗り越えられますよ
免責事項
本記事の内容は、公開時点での各種公式情報・調査データに基づいて構成しておりますが、制度や料金、運用状況などは変更される可能性があります。受験に関する最終的な判断やお手続きの際は、必ず英検協会などの一次情報をご確認ください。
なお、当記事には広告を含む部分があります。紹介しているサービスの利用を無理に推奨するものではなく、あくまでご自身に合った学び方を見つけるための参考としてご活用ください。



すべての受験者の方が、自分らしいペースで一歩踏み出せるよう、心より応援しております。









コメント