第1章 中期経営計画ブームの背景と実態
株価改革の波が呼び込んだ「中計ラッシュ」
近年、多くの上場企業が相次いで中期経営計画を打ち出す傾向が強まっています。とくに2024年には、過去最多となる約700社が中計を公表する結果となりました。この急増の背景には、2023年に東京証券取引所が打ち出した“資本コストを意識した経営”への強い要請が影響していると考えられます。
上場企業にとって資本効率の低さを放置することは、今や市場からの評価を大きく左右する要素となりました。株価純資産倍率(PBR)が1倍を割り込むような企業は、経営陣としての説明責任を問われる状況にあり、こうした圧力が「変革姿勢」の可視化として中計策定を促した構図が見て取れます。
とりわけスタンダード市場に上場する中堅企業では、従来あまり注目されてこなかった成長戦略の発信や資本政策の見直しが進み、中計策定を通じて企業価値の再評価を目指す動きが広がっています。
経営者が見据える「未来のスパン」は何年か
企業が中計を作成する目的のひとつに「経営の見える化」がありますが、その前提として問われるのが「どこまでの未来を想定しているか」です。ある調査によれば、上場企業の最高財務責任者(CFO)のうち約4割が「おおむね3年先」、同じく4割が「約6年先」を経営の視野に入れているという結果が出ています。一方で、「10年以上先」を見据えると回答した企業は全体の2割に満たず、まだまだ長期的視点を経営に組み込む企業は少数派にとどまっている状況です。
この結果は、中計の策定自体が“短中期の施策整理”という意味合いに留まっており、構造的な変革や将来シナリオへの対応といった長期テーマとは切り離されている可能性を示唆しています。
株式市場の期待と現実のギャップ
中期経営計画は本来、企業の将来像を市場に提示する重要なコミュニケーションツールですが、その発表が常に好感をもって受け止められているわけではありません。実際に、2024〜2025年にかけて中計を公表した約1,000社について分析したところ、発表後10営業日で株価がプラスとなったのは平均0.2%にすぎませんでした。しかも、中央値で見ると0.6%の下落を記録しており、むしろ半数以上の企業で市場評価が悪化した形となっています。
この背景には、中計に対する市場の見方が厳しくなっていることがあります。とくに、抽象的な数値目標の羅列に終始した計画は、投資家の失望を誘発するリスクがあるという指摘も聞かれます。結果として、中計の公表が「市場との対話の場」である以上に、「高リスク・低リターンのイベント」になりつつあるという現実も無視できません。
中期目標がもたらす副作用
さらに注意が必要なのは、中計が内部マネジメントに与える影響です。目標達成を最優先するあまり、計画期間中の投資を抑制してしまうケースが後を絶ちません。本来は未来への布石となるべき研究開発や人的資本への投資が先送りされ、結果として中長期的な成長機会を失うという問題も指摘されています。
こうした中計偏重の姿勢は、経営の柔軟性を損なう要因にもなりえます。形式上の整合性にこだわるあまり、経営戦略の本質を見誤るリスクは常に存在しています。その意味では、中計の存在意義そのものを再考する動きが、一部の企業で出始めているのも自然な流れと言えるかもしれません。
第2章 長期視点が利益を押し上げるメカニズム
短期か、長期か──明暗を分ける利益成長率
経営の視野がどの程度先を見据えているか。それが企業の収益性に与える影響は小さくないようです。直近の営業利益の伸び率を比較したデータによると、おおむね3〜6年を視野に経営している企業の平均伸び率が18%にとどまった一方で、10年以上先を見据えた企業群では52%という高い伸び率が確認されています。
この差は一時的な業績変動に起因するものではなく、継続的な投資や事業構造の最適化が、複利的に成長へ寄与している可能性を示唆しています。言い換えれば、目先の数字を積み上げる戦術と、将来像から逆算して打ち手を整える戦略との違いが、利益という形で明確に表れていると考えられます。
人的資本への投資が生む複利効果
こうした長期的な収益成長の背景には、人材への投資姿勢が大きく関係しています。短期的なコスト削減にとどまらず、組織のスキルや文化に対して計画的な投資を継続できる企業では、生産性向上とともに競争力が高まりやすくなります。
たとえば、ある小売企業では、人的資本に関する投資の収益率が、従来の店舗投資を上回ると試算されています。これは、人材の成長が直接的に事業の付加価値につながることを示す一例です。さらに、従業員のスキルアップやキャリア支援といった取り組みが、賃金上昇や企業価値の持続的な向上にも波及する構造をつくり出しているようです。
他方、中小企業では外国人材の登用や大手企業出身者の活用によって、多様な視点や知見を取り込む動きもみられます。こうした柔軟な戦力編成が、労働人口減少という構造課題に対する一つの対処策となっているケースも見受けられます。
長期的な投資判断と事業ポートフォリオの再設計
長期的視点で経営に取り組む企業ほど、将来の市場機会を見据えた設備投資や研究開発を惜しまない傾向があります。こうしたスタンスは一見、短期の利益率を圧迫する要因と見なされがちですが、中長期的には企業の競争優位性を築くための基盤強化に直結します。
実際に、長期目線を重視する企業では、経営資源の配分に明確な意図がみられることが多く、限られた資本をどこに集中すべきかという意思決定の質にも影響を与えています。加えて、不採算部門からの撤退や再編を機動的に実行することで、全体としての事業ポートフォリオが洗練される傾向も強まっています。
このような企業では、事業成長のための“種まき”が継続的に行われており、それが将来的な新収益源の創出につながっているとみられます。
社会課題との共存を目指す企業経営
加えて近年では、サステナビリティへの対応も経営における重要な判断軸のひとつとなってきました。たとえば、ある小売系企業では、2050年を見据えた長期計画を策定し、脱炭素や人的資本の強化、さらには再生可能エネルギーの活用といった非財務的価値の向上に注力しています。
こうした姿勢は、一見すると利益追求とは距離があるように思われがちですが、結果的には株価の上昇やブランド価値の向上につながっている例も見られます。社会課題の解決と利益の両立を目指す姿勢そのものが、長期的な市場からの信頼を得る要因となっている可能性も否定できません。
成長の原動力としての「時間軸」
以上を踏まえると、経営における「時間軸の設計」が業績に与える影響は決して軽視できないといえるでしょう。短期の目標管理に偏ると、見えづらいリスクや機会を取りこぼす恐れがあります。逆に、10年、20年という長いスパンで事業構想を描くことで、より柔軟かつ本質的な戦略が選択できる環境が整います。
こうした長期的スタンスは、企業内部における意思決定の質や人材育成の仕組みにも波及しており、結果として財務指標にも好影響を与えているケースが多い印象です。もちろん、すべての業種・企業に一律に当てはまるとは限りませんが、長期視点がもたらす可能性については、より多くの企業が真剣に向き合うべき段階に差し掛かっているのではないでしょうか。
第3章 “中計病”からの脱却──長期経営に舵を切る実務ポイント
数値目標を外したことで見えたもの
中期経営計画(中計)の形骸化に対する問題意識から、目標の定量的な提示を取りやめる動きが一部で広がっています。かつては3カ年の売上高や営業利益目標が明示されることが通例でしたが、近年はより柔軟で機動的な経営戦略を優先する傾向が見られます。
ある大手製造業では、明確な数値目標の提示をやめる代わりに、部門間の横断的な連携による成長を主眼とする中計を策定しました。その結果、経営資源の流動性が高まり、部門ごとの“縦割り最適”を超えた戦略統合が進展したという声も聞かれます。株式市場もこうした変化を好意的に受け止め、結果として株価の大幅な上昇につながった事例も存在します。
中計をやめた企業に起きた変化
中計を公表しないという決断に至った企業では、従来の「予算ありき」の施策運営から脱却し、経営方針を大きく見直す動きが確認されています。たとえば過去に中計達成を優先するあまり、過剰な新規開拓やリソース負担により離職者が相次いだというケースでは、以降、長期視点への転換が図られました。
このような背景のもとで導入されたのが、「100年先を見据える」という超長期ビジョンです。経営の重心を数値管理から人的資本や事業モデルの持続性へと移し、社員の成長や内製技術の強化を起点に経営を再構築する方針が明確化されています。結果として、生産性の改善や利益率の向上に加え、離職率の安定化もみられるようになったようです。
長期ビジョンを実装するための4つの軸
こうした長期指向の経営を実務に落とし込むには、単なるスローガンにとどめず、具体的なフレームワークを設計する必要があります。とくに次の4つの要素は、戦略構築の基礎となる重要な視点です。
- 市場環境シナリオ
将来の社会・産業構造の変化に対し、複数の仮説を想定したうえで戦略を柔軟に設計する必要があります。 - 人材育成ロードマップ
5年後・10年後に必要となるスキルセットや職種像を見据え、逆算した研修設計や人事施策を展開します。 - 資本配分の原則
限られた資金をどの領域に投下するか、その優先順位と判断軸を明確に持つことが求められます。 - 事業ポートフォリオの再編基準
成長領域への集中と、低収益部門の整理を進めるための基準やプロセスをあらかじめ設定することが重要です。
これらを踏まえ、経営判断が属人的なもので終わらず、組織全体としての合意形成と継続性を確保するための設計が不可欠です。
市場と向き合うエンゲージメント戦略
一方で、長期志向を貫くにあたって避けて通れないのが、短期的リターンを重視する投資家との対話です。ここで問われるのは、「なぜ目先の目標を掲げないのか」「長期投資の見返りはいつ訪れるのか」といった問いに、納得性ある情報をもって応える準備があるかどうかです。
たとえば、非財務領域(人的資本・知的資産など)のKPI開示や、資本コストを考慮した配当方針の明示、さらには中長期IRの充実といった施策が、エンゲージメント向上の一助になります。企業と市場との双方向的な意思疎通が進むことで、短期と長期の価値観の接点が見出され、持続可能な資本政策が形成されていくものと考えられます。
免責事項
本記事は、公開されている報道資料・調査結果に基づき、筆者独自の編集方針により再構成した情報提供を目的とするコンテンツです。
内容には正確性を期していますが、将来の経営判断や投資行動等について何らかの保証を行うものではありません。
また、本文中に記載される企業の取組・数値・事例はあくまで一般論としての紹介であり、特定企業への推奨や批判を目的とするものではありません。
経営・会計・財務に関する実務的な意思決定を行う際は、専門家等への個別相談を併せてご検討ください。
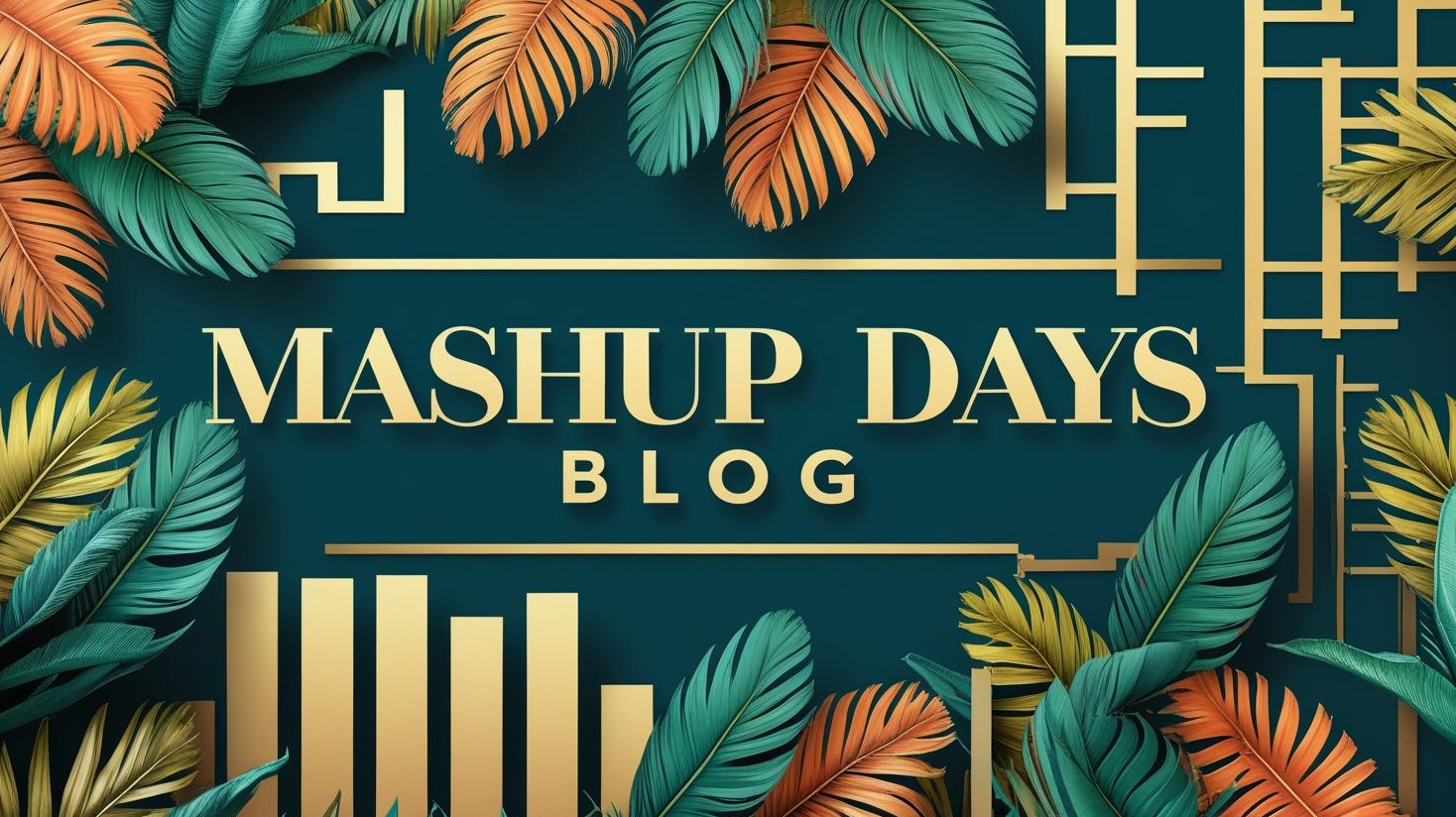








コメント