第1章 米国25%輸入車関税が突きつける現実
自動車産業を直撃する「通商拡大法232条」の発動
2025年4月、米国政府は通商拡大法232条に基づき、輸入自動車およびその基幹部品に対して25%の追加関税を発動しました。この措置により、日本からの自動車輸出は直接的な打撃を受けることになりました。米国の制度上、国内の安全保障や産業保護を理由に通商制限をかけることが可能とされており、自動車も例外ではないという立場です。
この関税には、完成車だけでなくエンジンやトランスミッションなどの主要部品も含まれており、自動車メーカーにとっては完成品だけでなく部材調達コストの増大という二重の負担が課せられる結果となっています。一方で、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に準拠する車両や部品には免除措置があるものの、実際には多くの企業がその対象外となり得る現実があります。
米国国内での生産に対しても、輸入部品に課される関税の一部が軽減される制度は設けられているものの、その恩恵を受けられる企業は限定的です。結果として、自動車メーカーは生産体制の根本的な見直しを迫られています。
経営計画に影を落とす収益悪化の試算
この新たな関税措置は、具体的な経営数値にも大きな影響を及ぼし始めています。ホンダは2026年3月期における営業利益が、前期比で59%減となる5,000億円規模に落ち込む見通しを示しました。このうち、関税に起因する利益押し下げ要因は実に6,500億円にのぼります。
内訳としては、完成車の関税負担が3,000億円、部品・原材料に係る負担が2,200億円、さらに二輪車やその他事業での影響が1,300億円と試算されています。また、ホンダは輸出入台数や単価に基づき、最大で年7,000億円規模のインパクトを受け得るとの試算も併せて公表しています。
加えて、為替レートを1ドル=135円と保守的に設定した場合、これによる減益影響も4,520億円に達するとされており、単なる関税措置にとどまらない外部リスクが収益構造全体に重くのしかかっている状況です。
日産についても、同様に最大4,500億円の減益が関税によって生じる可能性があるとされています。こうした影響は、日本車メーカー全体に波及し得る性質のものであり、1社単独での対応では限界があるという認識が徐々に広がりつつあります。
日米交渉を難航させる「相互関税」という構造的対立
今回の関税導入は、単なる単発の通商制限ではなく、「相互関税政策」の一環として日本を含む諸外国との交渉材料にもなっています。米国側の立場としては、対日貿易赤字の削減と国内産業の保護を軸に、関税の維持を強く主張している状況です。
一方で、日本政府としては、自動車産業が国内経済の中核を担う基幹産業であるという認識のもと、関税撤廃・引き下げを粘り強く求めています。交渉の焦点は自動車関税だけにとどまらず、非関税障壁の撤廃や、円安を巡る為替政策の問題にも波及しており、議論は多層的です。
交渉の経緯を振り返ると、2025年春から夏にかけて集中的に協議が行われましたが、両国間の立場の隔たりは大きく、7月にはトランプ大統領が「合意は困難」との認識を示し、さらなる追加関税も辞さない構えを見せています。こうした状況下において、日系自動車メーカーにとっての中長期的な事業計画は、不確実性を増すばかりです。
米国現地生産が経営の命綱になる理由
25%という高率な関税が恒常化する見通しとなる中、日本の自動車メーカーはグローバルな生産・販売戦略の再構築を余儀なくされています。実際に、米国市場における販売車両のうち、日産は47%、ホンダは32%を米国外から輸入しています。これらの比率が高い企業ほど、関税の影響を直接かつ重く受けることになります。
特に、輸入比率の高い完成車と主要部品が同時に関税対象となったことで、製造コスト全体が上昇。価格競争力の低下を招き、販売台数そのものが減少する懸念もあります。こうしたリスクを低減するためには、北米での生産比率を引き上げ、現地調達・現地組立によって関税の枠外に出るしか方法がありません。
この点において、日産とホンダの協業による現地生産体制の構築は、単なるコスト対策にとどまらず、経営の持続可能性を支える重要な柱となり得ます。時間を要する自社投資に比べて、OEM供給という形式で短期的に生産を拡大できる枠組みは、戦略上の合理性も高いと考えられます。
関税は企業だけでなく“産業全体”に広がる課題
今回の措置が突きつけているのは、単に収益減少という損益上の問題だけではありません。自動車産業は裾野の広い産業であり、完成車メーカーが受ける影響は、部品メーカー、物流事業者、原材料サプライヤーにまで波及します。
また、日本経済において輸送機器は輸出総額の大きな割合を占めており、この分野での国際競争力が低下すれば、雇用や地方経済にも少なからぬ影響が及びかねません。したがって、関税政策の対応は、個別企業の経営戦略にとどまらず、日本全体の産業構造を見直す契機として捉える必要があると言えるでしょう。
第2章 日産×ホンダ協業が描く“工場フル稼働”シナリオ
稼働率57%──キャントン工場が抱える重い現実
日産自動車の米国ミシシッピ州キャントン工場は、2024年時点で稼働率が57%にとどまっています。一般的に、自動車工場の損益分岐点は稼働率でおおむね80%前後とされており、この水準を下回る状態が継続すれば、固定費の吸収が困難となり、収益性は大きく損なわれます。
実際、日産はすでに工場の稼働率低下を受け、生産体制の見直しや従業員の配置転換など、経営の効率化に向けた対策を講じてきました。しかし、生産ラインの完全な閉鎖には至っておらず、過剰なキャパシティを維持したまま、低稼働が続いている構図となっています。こうした状況の中、キャントン工場を活用したホンダ向けOEM生産の打診は、経営合理性の高い選択肢として注目されています。
OEM供給──ホンダブランドを日産が生産するという仕組み
今回の協業案では、日産がキャントン工場でピックアップトラックを製造し、その車両にホンダのブランドロゴを装着したうえで、ホンダが自社ブランド車として米国内で販売する、というスキームが検討されています。
OEM供給の実務的な流れとしては、日産が既存の生産ラインを用いてピックアップトラックを組み立て、その最終工程でホンダのブランドロゴを取り付けます。その後、完成車はホンダが調達・販売し、ディーラー網やマーケティングなどはホンダ側のチャネルを用いて展開される形となります。
ホンダにとってこの方式の利点は明確です。従来、ホンダは米国市場において、日常利用に適したピックアップトラックを展開してきましたが、今回の協業により、より本格的なトラック性能を備えた大型モデルのラインアップを一気に拡充することが可能になります。
設備・開発投資の最小化とコスト合理化の相乗効果
両社の協業がもたらすもう一つの重要な意義は、開発・生産の重複投資を回避しながら、コスト削減と時間短縮を両立できる点にあります。
たとえば、車両開発においては、車台(プラットフォーム)の共通化や、制御ソフトウェアの共同開発によって、数百億円規模の投資を抑制できる可能性が示されています。こうした共通化によって、開発サイクル全体の短縮と資源配分の効率化が期待されます。
また、生産設備に関しても、新たな製造ラインを建設することなく、既存のキャントン工場を活用することで初期投資の抑制につながります。工場を共有するという形式により、日産は稼働率を引き上げて固定費を吸収し、ホンダは生産までの立ち上げ期間を大幅に短縮できるという、互いの経営課題を補完し合う構図が浮かび上がります。
さらに、部品の共通化を進めることで、調達面でもスケールメリットが発揮され、1点あたりの部品単価を引き下げられる可能性もあります。これは、現在のように為替や原材料価格の変動リスクが高まる局面においては、特に重要な管理項目となり得ます。
関税対応と収益構造の再構築を両立させる取り組み
今回のOEM協業には、関税回避という明確な経済的インセンティブも存在しています。米国で完成車を生産することによって、25%の関税負担を免れることができれば、日産・ホンダ両社にとって収益への影響は大きく異なってきます。
実際に、ホンダは関税によって6,500億円、日産は4,500億円の営業利益を押し下げられるリスクを抱えており、こうした高率課税への対応策は経営の優先課題となっています。現地生産を拡大し、米国外からの輸入比率を引き下げることは、両社が直面する共通課題への現実的な解決策として位置づけられています。
さらに注目すべきは、今回のような連携が日米通商交渉にも影響を与える可能性がある点です。日本の自動車メーカーが米国内での生産強化を表明すれば、それ自体が交渉材料として米国側への一定のメッセージとなり得ます。政治的な側面を意識した戦略判断という視点でも、現地生産シフトは意味を持つものとなっています。
協業下におけるブランドと品質の取り扱い方
OEMによる協業が成立する際には、ブランド価値や品質保証の役割分担を明確にしておく必要があります。今回の構想では、日産が工場で生産を行い、ホンダが販売を担う形で責任分界が整理されています。
つまり、製造段階における品質管理責任は日産が負い、販売後の保証対応やアフターサービスについてはホンダが担当するという形です。このような明確な分担によって、顧客の信頼を損なうことなく、両社のブランドを守りながら協業を円滑に進める土台が形成されています。
また、こうしたブランド供給型の協業は、単なるコスト削減の枠を超え、各社が得意とする分野に特化して事業効率を高めていくという意味でも、現代のグローバル製造業において合理的なモデルと評価されています。
第3章 再統合を見据えた中長期ロードマップ
電池供給体制の共有化──協業深化の一歩
日産とホンダの協業関係は、完成車のOEM供給にとどまらず、次世代の電動化基盤でも広がりを見せています。具体的には、ホンダと韓国LG系による北米での合弁電池工場から、2028年以降、日産に対して車載電池を供給する構想が浮上しています。
この供給スキームが実現すれば、ホンダ側にとっては生産規模の拡大と設備投資の回収効率化につながり、日産側にとっては電池調達先の多様化と安定確保という実務的な利点があります。急成長が見込まれるEV市場において、バッテリーのサプライチェーンを巡る競争が激しさを増す中、協業による相互補完の効果が期待されます。
また、供給側であるLGエネルギーソリューションの経営陣も、この日産向け供給構想に対して前向きな姿勢を示しており、日本メーカーとの連携を通じて北米市場での存在感を高めたい意向がにじみ出ています。
EVと自動運転での共通基盤開発が加速
ホンダと日産が協業を進めるもう一つの柱が、EVおよび自動運転分野における基礎技術の共通化です。これまで両社は独自に車載OS(オペレーティングシステム)や自動運転用ソフトウェアを開発してきましたが、近年は制御技術の複雑化と開発コストの増大を背景に、共同研究の必要性が高まっています。
たとえば、ホンダが開発中の車載OSは、日産との共通仕様化も視野に入れており、今後は両社による共同設計・実装が現実味を帯びています。これにより、車載ソフトの開発コストを分担しつつ、性能や安全性の水準を揃えることができ、次世代EVでの仕様統一による量産効果も期待されます。
また、電動駆動装置「e‑Axle」の仕様共通化も重要なテーマの一つです。モーター・インバーター・減速機を一体化したこの装置は、EVの性能とコストを左右する重要部品であり、共通化によって部品点数を絞り、量産によるコスト圧縮を図る戦略が想定されています。
加えて、充電インフラの最適化やEV用電池の標準化など、車両周辺領域においても両社の協業は進行中です。EVの普及には個別車両の性能だけでなく、ユーザーが安心して利用できる環境整備が不可欠であるため、こうした共通化は中長期的な競争力強化に直結します。
中国勢の台頭と日本勢の選択肢
北米市場において、日産とホンダの協業を取り巻く外部環境として、中国系自動車メーカーの急速な台頭も見逃せません。とくにEV分野では、中国メーカーが価格競争力と技術力を武器に、市場での存在感を急速に強めています。
日産はハイブリッド車の投入時期が後れたことで北米市場での販売に苦戦しており、そこに中国勢が低価格EVやHVで攻勢をかければ、競争環境はさらに厳しくなります。また、中国メーカーはサプライチェーンの自社内完結や低コスト部品の調達力を強みとしており、日本勢の部品コスト構造に対する一つの警鐘となっています。
一方で、こうした競争環境は、日産とホンダが協業を通じてコスト競争力と開発スピードを高める動機にもなっています。中国勢に対抗するには単独での対応では限界があり、国内メーカー同士がリソースを共有し、開発・生産両面でシナジーを創出していくことが求められる局面にあるといえます。
世界3位連合への再統合シナリオとそのハードル
今回の協業は、将来的な経営統合を視野に入れた布石と捉える向きもあります。かつて、日産とホンダは世界3位の自動車連合を目指して統合協議に入った経緯があり、協業が深化すれば再び統合の道筋が開かれる可能性もあります。
その実現には段階的なプロセスが必要とされます。まずは、現在進めているEV・自動運転分野での技術協業を軸に、相互依存を強める。次に、生産拠点の相互活用や部品の共同調達などを通じて、実務レベルでの連携を深化させ、信頼関係を蓄積していく。そのうえで、経営統合という最終段階に進むか否かを検討する、という流れが現実的なシナリオといえます。
ただし、乗り越えるべき課題も多く残されています。ホンダは過去の協議破談の理由として、日産の経営体制に対する不信感を挙げており、体制の刷新と透明性の向上は不可避とみられます。また、企業文化や意思決定プロセスの違い、主導権争いのリスクなど、制度面・人事面の統合課題も依然として残っています。
両社が実効性のあるリストラ策を着実に進め、EV戦略を加速できるかどうか。協業を通じて、将来の統合に向けた信頼の下地を丁寧に築けるかどうか。これらが統合実現への分岐点となる可能性が高いと考えられます。
関税交渉への波及──企業の動きが外交カードに
日産とホンダの協業が進展することで、日米間の自動車関税交渉にも一定の影響が生じる可能性があります。日本の自動車メーカーが現地生産を拡大すれば、米国政府に対して「国内雇用に資する存在である」とのメッセージを発信することになり、関税政策の見直しを促す交渉材料となるかもしれません。
一方、こうした動きは日本側にとっても、交渉カードの一部として活用できる要素となります。企業側の対応と政府間の交渉が相互に作用し合いながら進むという構図は、これまでの貿易協議の中でもしばしば見られる傾向です。
今回の協業は、単なる事業戦略にとどまらず、通商政策や外交上の駆け引きにまで影響を及ぼす可能性がある点でも、今後の展開に注目が集まります。
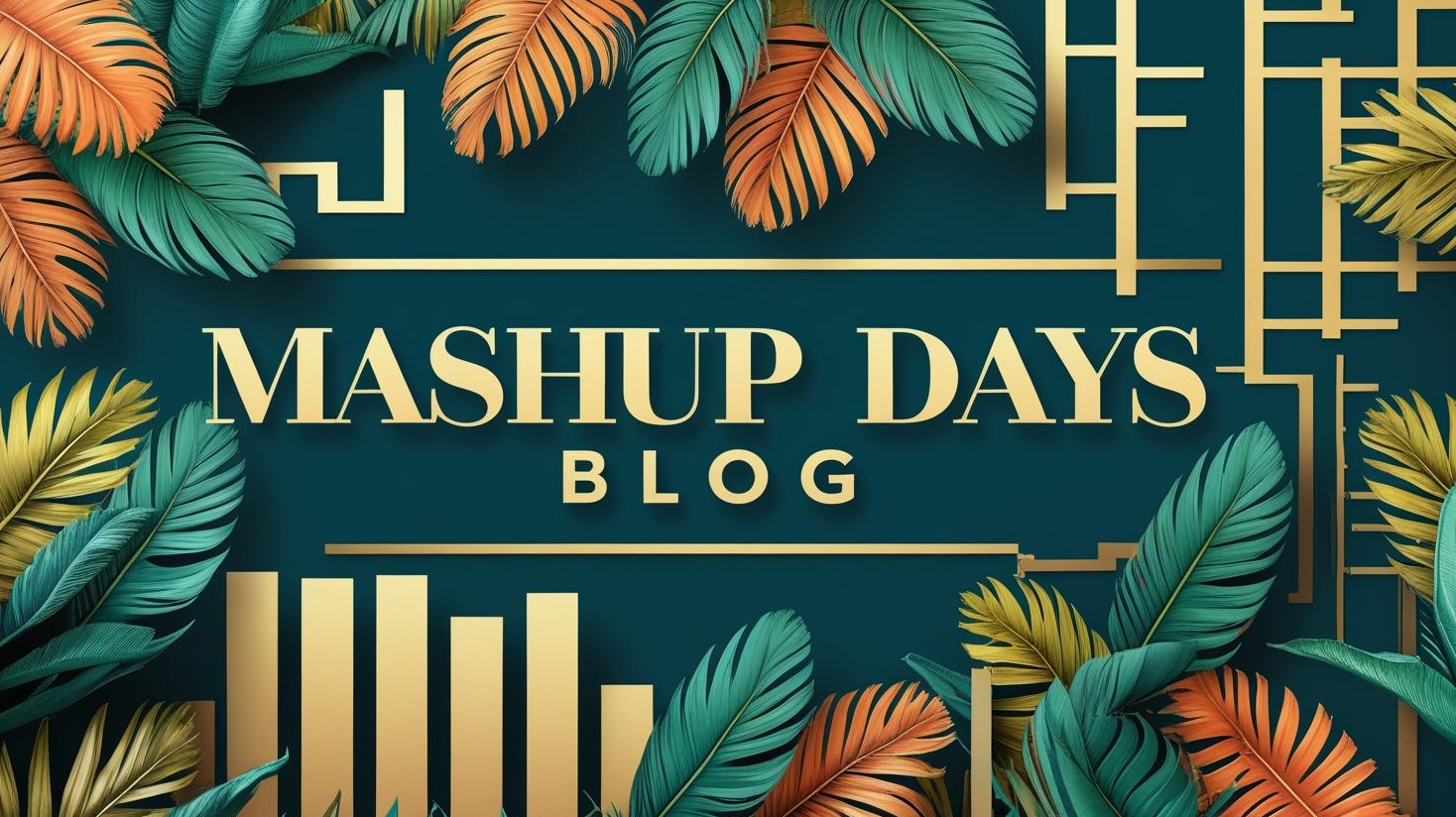








コメント