第1章|「第3の場所」が色あせる理由──ブランド希薄化のメカニズム
革新的だった空間価値が揺らぎ始めた
スターバックスが拡大の礎として掲げてきた「第3の場所」というコンセプトは、かつて同社の象徴的な強みとされてきました。職場でもなく、自宅でもない──人々がふと立ち寄り、思い思いの時間を過ごせる第三の拠点として、スターバックスの店舗空間は多くの顧客に受け入れられてきた背景があります。
しかし近年、その空間価値が以前ほど魅力的に映らなくなってきているようです。日常の延長線上にあった“くつろぎの場所”が、単なる「商品受け渡しの場」へと変わりつつある印象を受ける方も少なくないのではないでしょうか。
背景には、過去数年間における急速な出店拡大があります。米国では1ブロック歩けば店舗が見つかるほどの密度になり、世界的にもこの5年間で約3割の増加が見られました。かつての“特別感”は、次第に日常に溶け込み、その存在価値が希薄化しつつある状況に直面しています。
サービス品質のばらつきとフランチャイズ拡大の影響
顧客体験に変化をもたらしている要因のひとつが、サービスの一貫性の揺らぎです。とりわけフランチャイズ店舗の増加により、運営水準や接客品質に一定のばらつきが生じているケースが散見されます。ブランドイメージの統一が難しくなっている側面も否めません。
中には、椅子やテーブルのない店舗や、滞在を制限するような注意書きが掲示されるケースも報告されています。これまで「くつろげる空間」が当然のように提供されていた印象があっただけに、店舗によってはその期待が裏切られてしまうこともあるのかもしれません。
また、オンライン注文の普及に伴い、利用者の目的自体が変わってきている点も見逃せません。アプリで事前注文し、商品を受け取るだけの“通過型”店舗の割合が増えるなかで、従来のように時間を過ごす空間としての役割が相対的に薄れてきています。
店舗あたり売上の停滞が映し出す構造課題
こうした変化は、数字にも表れています。2024年9月期の店舗あたり売上高は、前年度比で5%の減少となりました。10年前と比較して店舗数が2倍に拡大している一方で、同期間の店舗あたり売上高は17%の伸びにとどまっています。加えて、インフレの影響を加味すると、実質的には付加価値がほとんど増えていない既存店も少なくないと推察されます。
このような売上構造は、単なる景気動向にとどまらず、ブランドの希少性や空間価値の希薄化がもたらす長期的な収益基盤への影響を示していると考えられます。客数の減少傾向はすでに5四半期連続で確認されており、構造的な改善を要する局面に差し掛かっているようにも見受けられます。
また、都市部の一部店舗では、トイレの利用目的で訪れる人が増加しているとの声もあり、店舗設計が本来意図していた顧客体験とは異なる方向に変質している可能性も指摘されています。
失われた「おしゃれさ」と「特別感」
かつて、スターバックスの店舗は「少し背伸びした空間」や「自分らしさを大切にできる場所」としての魅力を放っていました。日本国内でも、落ち着いた照明、木目調の内装、香り高いコーヒーとともに過ごす時間が、多くの利用者にとって日常の中の特別なひとときとなっていたことでしょう。
ところが、ブランドが広範に普及することで、その“特別感”が相対的に薄れてしまうのは自然な流れとも言えます。現在では、利便性やスピードを優先した運営が前面に出る場面も増えており、従来の顧客層が求めていた「くつろぎ」や「空間としての魅力」が後景に退いている様子も散見されます。
もちろん、こうした変化がすべてネガティブというわけではありません。注文の効率化や利便性向上は、現代的な消費行動に適合する取り組みでもあります。ただし、その結果として従来の価値軸が揺らいでいることは、事実として押さえておく必要があるでしょう。
第2章|再建請負人ブライアン・ニコルの処方箋──原点回帰と拡大策の両輪
経営トップの交代が意味するもの
2024年、スターバックスの経営体制に大きな変化が訪れました。前CEOの在任がわずか1年半で終了し、後任として迎えられたのがブライアン・ニコル氏です。過去に外食企業の立て直しを成功させた経歴を持つ人物であり、その実績が高く評価されたことが就任の背景にあると考えられます。
ニコル氏は、新型コロナウイルスの影響を経た店舗運営の課題、既存店の売上減少、そしてブランド価値の揺らぎといった多層的な問題に直面しながらも、変革の必要性を正面から受け止めています。報酬条件も極めて高額であることから、社内外ともに高い期待が寄せられていることは間違いありません。
経営再建の本格始動にあたって、同氏が最初に打ち出した方向性は「原点回帰」と「拡大戦略」の両立です。一見、相反するようにも映るこの2つの柱が、スターバックス再生の鍵を握っているといえるでしょう。
原点回帰に向けた現場主義のアプローチ
ニコル氏の改革は、現場の感覚に根ざした取り組みから始まっています。象徴的な施策のひとつが、店内での陶製マグカップの復活です。これは、単に環境配慮という側面だけでなく、「滞在したくなる場所」を再びつくり上げるという意図が込められているものと読み取れます。
また、オペレーション面でも見直しが進められており、注文から提供までの時間を最長4分以内に抑えるという新たな基準が導入されています。この時間目標は、顧客満足度の回復を目的とした具体的な数値目標であり、現場スタッフにとっても明確な指針となり得るでしょう。
さらに、利用客以外のトイレ利用を制限するルールの導入や、従業員のドレスコード刷新といった細やかな対応も進められています。これらはいずれも、ブランド体験の質を再構築しようとする姿勢の表れと考えられます。
加えて、世界各国の優秀なバリスタを招集して技術を競う場を新たに設けたことも注目に値します。接客技術や商品提供力の強化は、サービス業としての本質に立ち返る動きとも言えるでしょう。
攻めの姿勢を崩さない成長戦略
一方で、ニコル氏が掲げる成長ビジョンは非常に野心的です。北米市場における店舗数を2倍に増やす方針を明言し、さらにグローバル展開についても、同様の成長可能性を見出している国が複数存在するとしています。
こうした拡大方針は、従来の縮小均衡的な対応とは対照的です。実際、過去には経営悪化を受けて800店舗以上の閉鎖を余儀なくされた時期もありましたが、今回の戦略では「縮小による改善」ではなく「投資による成長」を選択肢として掲げています。
成長投資を進める意図としては、単に売上回復を図るというよりも、ブランドの再活性化と市場支配力の維持が主眼にあるとみられます。ニコル氏は、単にコスト削減による短期的な改善ではなく、中長期的なブランド価値の再定義を視野に入れているようです。
もちろん、過去に同氏が経営を立て直した企業とスターバックスでは、店舗規模や事業構造に大きな違いがあります。しかし、品質と拡大の両立を成功させた経験を持つ人物である以上、そのアプローチがまったく再現できないとは言い切れません。
両輪で進める改革がもたらす示唆
ここまで見てきたように、スターバックスが進めている経営改革は、店舗体験の質的向上と、戦略的な店舗数拡大の二軸で進行しています。どちらか一方に傾倒するのではなく、両立を図ろうとする点に特徴があるといえます。
ただし、これは決して容易な選択ではありません。拡大に伴って現場のオペレーションが追いつかなくなれば、かえってブランド毀損を招くおそれもあるためです。だからこそ、従業員教育や設計思想の再構築といった“根っこの部分”への投資が不可欠になります。
今後の成否を占ううえで重要となるのは、この二本柱がどれだけ連携して機能するかです。いずれかが崩れれば全体が不安定になる構造であることは否定できません。
とはいえ、トップ自らが改革の旗を振り、かつ現場レベルまで踏み込んで改善を進めている姿勢を見る限り、単なる理念倒れで終わるリスクは低いのではないかと考えられます。次章では、この両輪経営の裏にあるリスクや脆弱性を、財務・労務・市場環境といった視点から掘り下げてまいります。
第3章|質量二兎を追う経営のリスクと論点──財務・労務・競争環境を読む
キャッシュフローと資本構造の持続性
現在のスターバックスは、原点回帰と成長投資を両立させる経営戦略を進めるなかで、財務的な負荷にも直面しています。2025年3月末時点の手元現金は26億ドルと、新型コロナウイルスの影響が色濃く残っていた2020年3月末以来の水準にまで減少しました。これに対して、フリーキャッシュフローはおおむね30億ドル台を維持しており、一定の投資余力は残されています。
もっとも、資本面に目を向けると債務超過の状態にあり、健全性に対する市場の懸念が払拭されているとは言いがたい状況です。もちろん、高収益を維持できていれば、こうした資本構造自体が直ちに経営に影響を及ぼすとは限りません。しかし、収益性の変動が大きくなった場合には、資本構成が経営判断に一定の制約を与える可能性も否定はできません。
さらに、2025年1〜3月期の四半期決算では、純利益が前年同期比で半減しており、これが5四半期連続の最終減益となっています。こうした収益性の低下は、戦略的投資の進行と同時に、既存店売上の足踏みにも起因していると考えられます。
労働環境を巡る不確実性
経営戦略の実行にあたっては、人的資源面の課題も見過ごせません。スターバックスでは、米国国内で労働組合との対立が続いており、これはブランドイメージや従業員の定着率にも影響を及ぼしているとみられています。
2021年に初めて店舗単位で組合が結成されて以降、加盟店舗は500を超えました。その後も、賃上げや人員体制の見直しを求める動きが続き、2024年12月にはストライキが12州にまで広がったとされています。これらの動きは一部にとどまるとはいえ、企業全体としての対応姿勢が注目される要因になっていることは確かです。
2025年1月には、顧客および従業員以外の店舗利用を制限する方針が明らかになり、一定の秩序回復を図る姿勢も打ち出されました。ただし、根本的な合意形成には至っておらず、引き続き交渉が続けられている状況とみられます。労使間での関係構築が進まなければ、サービス品質の維持や現場のモチベーション管理にも波及するおそれがあります。
中国・日本市場の行方と競争環境
事業の地域的分散という観点からは、中国と日本における展開も重要な意味を持ちます。特に中国市場については、現地資本との競争が激化する中で、価格戦略の見直しなどが求められており、既存店の売上にも足踏みがみられています。一部では、事業の一部売却や資本再編の可能性が報じられたこともありましたが、現時点でその方針が正式に示されたわけではありません。
一方、日本市場では、年100店舗前後の出店を維持しながら、2000店体制を視野に入れた拡大が進められています。コンセプトを明確にした新型店舗の展開も並行して進められており、比較的安定した市場と見られる一方で、既存顧客との関係性をどう維持するかが今後の課題となりそうです。
加えて、外食業界全体としては、低価格帯の競合企業や新興ブランドの台頭も見られ、従来のようなブランド優位性だけで顧客を確保し続けることは難しくなってきていると考えられます。
質と量の両立に必要なマネジメント視点
こうした多面的な課題を踏まえると、スターバックスの今後においては、出店戦略と現場オペレーションを統合的にマネジメントできる体制づくりが求められるでしょう。人材育成、設計思想、メニュー構成、店舗ごとのカスタマイズ対応──これらを個別に考えるのではなく、総合的に調整する力が問われています。
また、労務面では対話の継続と制度設計の柔軟性が重要であり、財務面では収益性と資本健全性のバランスを見極めながら投資判断を下していく必要があります。質の高い体験を提供し続けることができれば、ブランドは再び成長軌道に乗る可能性を秘めていると考えられますが、それを支える仕組みが整っていなければ、成長戦略自体が空回りするおそれも否めません。
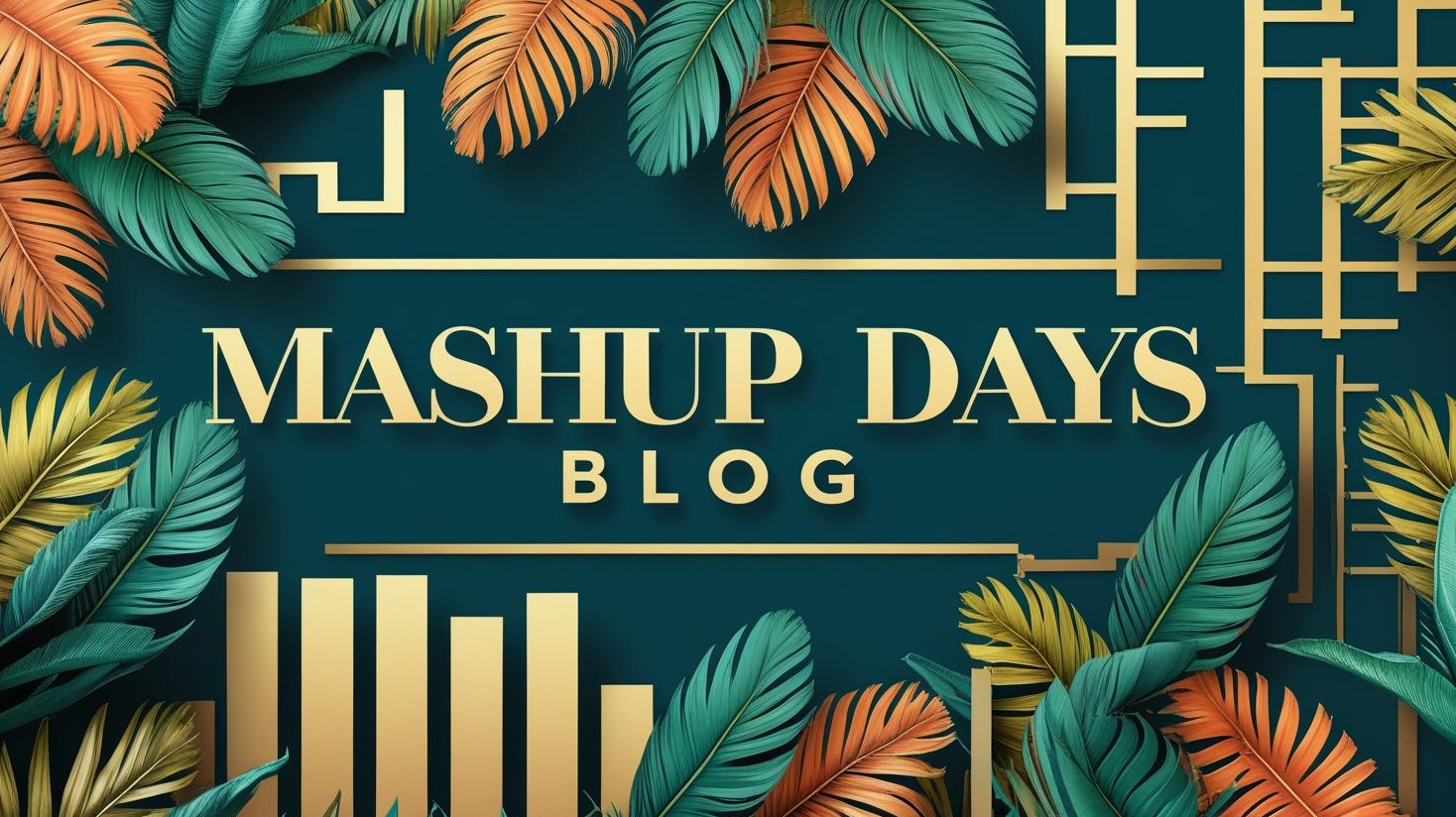








コメント