第1章|EV市場の転換点と追浜工場──日産×鴻海提携が示す選択肢とは
国内EVの現実──成長と鈍化のあいだで
電動化がグローバルの主流となる中、日本市場はやや異なる軌道をたどっています。普通乗用車におけるEVの新車販売比率は、2020年の0.59%から2023年には1.66%まで上昇しましたが、2024年には1.35%へと減少に転じました。プラグインハイブリッド車(PHEV)も含めても、EV+PHEVの合算シェアは3.06%と依然として小さく、主力はハイブリッド車(HEV)が担っている構図が続いています。
軽自動車分野においても、2023年には軽EVが約4万4000台(シェア約3.3%)販売されましたが、2024年は販売台数が約2万5000台(約2.1%)にとどまる見込みです。2025年1~4月期の速報値では、軽EV・普通車EVの合計シェアが1.30%に落ち込んでおり、短期的な拡大は難しい局面にあるといえるでしょう。
こうした動きは、市場が慎重な消費行動を取っていることに加え、価格・航続距離・インフラ整備のいずれも「決定打」に欠ける現状を反映しているものと考えられます。つまり、日本のEV市場は、今なお黎明期の範疇を脱していないという認識が必要です。
海外市場とのギャップ──成長速度と政策支援
これに対し、アメリカや欧州では明確な成長トレンドが見られます。米国では2024年時点でEVの販売シェアが8.1%、欧州(EU+EFTA+UK)では2025年1〜3月の時点で17.0%と、日本とは一桁違う水準に達しています。ただし、これらの地域でも政策支援の見直しや市場飽和による成長鈍化の兆しは見え始めており、今後の成長持続には不確実性も含んでいます。
特に米国では、政権交代によりEV義務化撤廃や税制優遇の見直しといった動きが出てきており、企業側も中長期戦略を見直す必要に迫られています。日本企業にとっても、こうした海外の政策変化は無関係ではなく、国内市場と海外戦略をどうバランスさせるかが改めて問われるタイミングに差し掛かっています。
追浜工場の現在地──稼働率と将来性の交差点
日産自動車の追浜工場(神奈川県横須賀市)は、1961年から稼働を続ける歴史ある主力拠点です。敷地面積約170万平方メートル、従業員数約3900人を擁し、生産設備のみならず、研究所、テストコース、専用埠頭まで備えた総合的な生産・開発拠点でもあります。
しかし、2024年時点での工場稼働率は約40%にとどまり、生産能力(約24万台)に対する稼働実績が損益分岐点を大きく下回っている状態が続いています。かつてはEV「リーフ」の生産を担っていた同工場も、現在はノート系車種に限定され、生産規模の縮小が進んでいます。
このような状況下で、追浜工場は日産の全体的な構造改革の一環として、統廃合候補に挙がることとなりました。ただし、他の工場と異なり、研究設備や物流機能などの資産性が高いことから、単純な閉鎖判断は容易ではありません。
鴻海との連携──再活用モデルとしての「受託EV生産」
こうした中、注目されているのが台湾・鴻海精密工業との協業です。鴻海は「CDMS(Contract Design & Manufacturing Service)」というモデルを掲げ、EVの設計・調達・製造までを一気通貫で請け負う受託生産体制を整えています。同社は海外で複数の自動車メーカーとの合弁事業を展開しており、ドイツのZFグループや中国企業との連携実績もあります。
今回の協議では、追浜工場における生産ラインの一部を鴻海のEV生産に活用する案が検討されており、日産としても余剰設備の有効利用と稼働率の向上が図れる形となります。仮に合弁が成立すれば、固定費の圧縮や雇用維持にもつながる可能性があるため、一定の現実味を帯びた選択肢として捉えられているようです。
また、追浜の立地と設備は、鴻海にとっても日本市場進出の足がかりとなり得る重要な資産であり、協業による相互利益が期待される構図です。もっとも、経営への関与の度合いや設備の共用範囲など、慎重な調整が求められる場面も想定されるため、拙速な判断は避けられるべきでしょう。
第2章|雇用・供給網・設備資産──追浜再活用に潜む経営合理性
雇用と稼働率のジレンマ──削減よりも活用の選択肢
日産自動車が経営再建の一環として工場の再編を進める中、追浜工場(神奈川県横須賀市)も例外ではありません。だが、その扱いには他拠点とは異なる慎重さが求められているようです。
というのも、追浜工場では2024年時点で約3900人の従業員が勤務しており、工場の稼働率は4割程度。これは、一般的に採算ラインとされる8割を大きく下回る水準であり、固定費の負担が経営にとって無視できないものになっていることを示しています。
このような状況だけを見れば、閉鎖や人員整理といった判断も浮上しやすいですが、現実にはそれほど単純な話ではありません。というのも、工場閉鎖にはリストラ費用や土地改変コストなど、一時的とはいえ大きな費用負担が発生します。さらに、周辺地域に根付いた雇用構造や、地元自治体との関係性も無視できない要素です。
こうした背景から、追浜工場の完全閉鎖ではなく、部分活用や他社との協業による稼働率向上といった「折衷案」が現実的な検討対象となってきたと見られます。
鴻海の受託モデル──生産機能の一部シェアによる補完
その打開策として浮上しているのが、台湾・鴻海精密工業との協業構想です。鴻海はすでに海外でEVの設計・製造を一括受託するビジネスモデル(CDMS)を展開しており、日本市場での生産拠点を模索していた状況にありました。
この構想においては、日産が自社工場の余剰ラインを鴻海に一部貸与し、同社がEVを生産する形が想定されています。仮に実現すれば、追浜工場の稼働率が改善されるのみならず、固定費の分担や生産技術の相互活用といった相乗効果も期待できます。
日産にとっては、工場閉鎖によるリストラリスクを回避できるうえ、施設の維持にも貢献する選択肢となり得ます。一方で鴻海にとっても、日本でのEV生産実績を確保できる意味合いがあり、互いの利害が一致しやすい構図だといえるでしょう。
もっとも、合弁や長期的な関与にまで踏み込む場合は、経営権や知財管理の在り方に注意が必要です。提携が進むにせよ、あくまで自社主導のライン管理が維持されることが、製造の品質や統制維持には不可欠です。
サプライチェーンと地域経済──雇用だけでは済まされない影響
追浜工場の存廃が注目される背景には、もう一つの要因があります。それが、地域に根付いた部品供給網への影響です。
日産系のサプライヤーは神奈川県内に2000社以上が集積しており、追浜を含む複数の完成車工場と直結しています。仮に追浜の機能が失われれば、部品の発注構造が変化することになり、一次・二次取引先を含む企業群に波及的な影響が出ることは避けられません。
さらに、このような地域密着型の供給網では、技術の蓄積や従業員の熟練度といった無形資産が多く存在しており、単なる雇用数だけでは測れない価値が形成されています。こうしたネットワークを維持するという観点からも、追浜工場の再活用は、単に「一工場の話」では収まらない課題を含んでいるといえるでしょう。
この点で、追浜工場の施設やラインを一部他社に開放しつつも、既存の部品調達網を維持しながら運用するという案は、供給体制全体の安定性を保つ意味でも理にかなったアプローチかもしれません。
設備資産の価値──「維持する」ことの経済合理性
追浜工場には、組立ラインだけでなく、衝突試験用の実験施設、テストコース、自動車専用船が発着可能な埠頭といった、高付加価値の設備が併設されています。こうした設備は一朝一夕では再構築できるものではなく、そのまま活用できる状態にあること自体が希少な資産だといえます。
実際、鴻海との協議でも、これらの試験施設などは引き続き日産が使用できる前提で話が進んでいるとされており、外部企業との共同利用であっても、基幹機能が毀損されないような設計が重視されているようです。
このように、製造と研究・評価の両輪を保持しながら、生産能力の一部を他社に活用させるスキームは、「手放さずに回す」柔軟な資産活用の一例と捉えることもできるでしょう。
第3章|提携戦略と制度リスク──EV・SDV時代における資本と政策の再構築
外資との関係性──協業と資本関与の境界線
EVシフトの本格化に伴い、自動車メーカー各社は単独での技術投資や生産拡張に限界を感じ始めており、国内外の連携を強化する動きが目立ちます。日産自動車と台湾・鴻海精密工業の間で進む協議も、その一つの象徴といえるでしょう。
ただし、鴻海がこれまでホンダにも提携を打診していた経緯があるように、EVやソフトウェアを中心とした開発領域では、技術連携と経営関与の境目が曖昧になる局面が出てきます。実際、日産の筆頭株主であるルノーとの関係調整にまで影響する可能性が取り沙汰されるなど、単なる製造委託にとどまらない議論へと発展している側面も見受けられます。
外資の経営参画に対しては、日本政府も一定の警戒姿勢を取っており、外国為替及び外国貿易法に基づく事前審査が求められるケースもあります。特に、車載半導体や電池、センサなどが戦略物資として認識される中、出資や提携のスキーム設計にはより一層の透明性と慎重な対応が求められると考えられます。
米国リスクの拡大──政策変更とコスト構造の揺らぎ
さらにグローバル展開を進める日系メーカーにとって、米国の政策動向は無視できない変数です。2025年以降、トランプ政権下で進められているEV義務化の見直しや関税強化は、北米市場に強く依存する日産を含め、多くの完成車メーカーにとって想定外のコスト増加要因となっています。
日産は、関税長期化によって最大で4500億円規模の減益リスクが生じる可能性を認識しており、米国生産拠点の最適化や現地部品調達の拡大といった対策を急いでいる段階です。ただ、こうした対応には一定の時間を要するため、短期的には価格転嫁や利益率の低下というかたちで業績に影響を及ぼすおそれがあります。
また、EVに対する政策支援が不透明化したことで、今後の新モデル開発や販売戦略の見直しを迫られる企業も増えつつあります。これは単に製品ラインの再構成にとどまらず、設備投資や研究開発投資のスケジューリングにまで影響する事態となる可能性も否定できません。
SDVという次なる競争軸──技術投資と主導権争い
加えて、EV市場の本質的な競争領域は、いまやハードウェアだけではありません。近年注目されている「ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)」は、車両をソフトウェアで制御・進化させるという新たな車づくりの概念であり、自動車産業全体がこの潮流に巻き込まれつつあります。
この分野では、車載OSや通信基盤の共通化といったテーマが重要性を増しており、トヨタやホンダを含む国内勢も独自OS開発や異業種連携を進めています。日産もEV「リーフ」などにSDV的な思想を導入する方向で動いており、将来的な主力技術のひとつとして育成する意向をにじませています。
一方で、SDVの実装には莫大な開発費がかかるため、外部パートナーとの連携やデータの共有・保護体制の整備が不可欠です。企業間でのデータアクセス管理やサイバーセキュリティ対策といった領域での国際競争も激化しており、日本勢がいかにして技術主導権を確保するかが、将来の産業構造に影響を及ぼすことになりそうです。
制度・資本・技術の三層管理が今後の焦点に
追浜工場をめぐる議論は、単なる国内拠点の再編では終わりません。外資との協業、米国市場の政策変動、そしてSDV開発競争という三層の変化が同時進行する中で、日産が取り得る経営判断の幅はかつてなく複雑になっています。
こうした状況においては、「提携か独立か」といった二項対立ではなく、資本・技術・制度という三つの軸をどうバランスさせるかが問われているといえます。追浜の再活用に向けた動きは、こうした多層的な課題を解きほぐすための一つの布石として見ることができるのかもしれません。
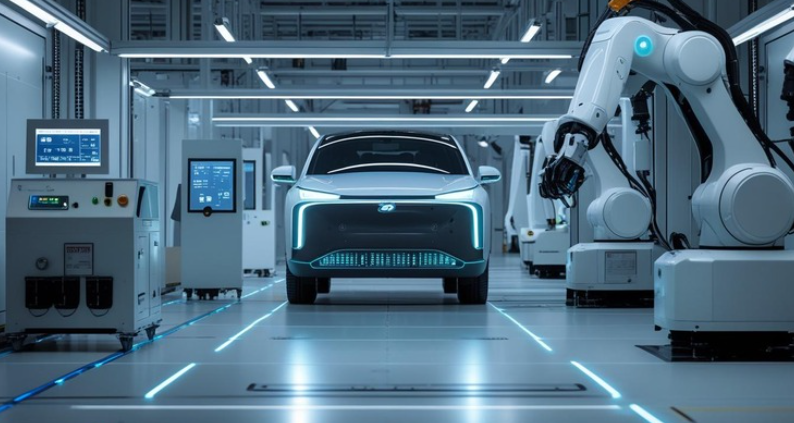








コメント